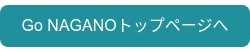発酵王国・長野県で「発酵バレーNAGANO」始動
長野県は全国の味噌生産量の半分以上を占め、日本酒の酒蔵の数は全国で2番目の多さを誇ります。最近ではワイン製造も盛んです。2018年には「発酵食品で人々の健康・長寿を目指す」として発酵・長寿県宣言を発表。これは長野県知事と、当時の長野県食品製造業振興ビジョン推進協議会会長であり、現在は一般社団法人発酵バレーNAGANOの理事長を務める青木時男(あおき・ときお)さんが共同で行ったものです。

「長野県の発酵文化は、紐解いていけばそれぞれに多様な物語がある」と、青木さん

長野県内、それぞれの暮らしに根付く形でさまざまな発酵食品が受け継がれている
青木さん「長野は発酵の最たる県であり、それらを裏付ける歴史や文化がある。豊かな自然に恵まれ、さらに最近では長寿県としても注目されています。発酵・長寿県宣言をした直後はイベントなどを企画し盛り上がっていましたが、コロナ禍で活動が停滞。食品業界全体が疲弊するなか、もう一度何かアクションを起こしたい思いで、発酵バレーNAGANOがスタートしました」
発酵を軸に業種の壁を越え、助け合いの精神をもって一歩踏み出していこう。そうして発酵に関連する8つの団体が連携し、コンソーシアムを設立したのが2023年11月のこと。これは全国でもはじめての取り組みです。
青木さん「私が代表を務めていた長野県味噌工業協同組合連合会の建物の隣に、長野県酒造組合の会館があるんですね。コロナ禍で活動が停滞するなか、『じゃあ日本酒はどうなんだろう』って状況を聞いてみたら、やはりコロナ禍で酒は悪者として扱われ、非常に厳しい状況だと言う。その時に改めて、業種を越えて情報交換しあい、共に考えることの可能性を感じました。同じように発酵に関する業種のみなさんに声をかけ、専門家の意見も聞きながらプロジェクトが進行していきました」
発酵バレーNAGANOの発案者となった青木さんは、県や国、これまでのコネクションも活かしながら、どうなるかわからない状況を、みんなの力で乗り越えてきました。
青木さん「従来の縦割りでは、自分が属する業種以外の団体が何をしているのかさえ分かりませんでした。コンソーシアムの設立はとても実験的な試みでしたが、やはり民間からのボトムアップで取り組むことに意味があったと思います。8団体の総意であれば、県や市町村など自治体との関係を構築しやすく、さまざまなプロジェクトに参画できる可能性が広がります」
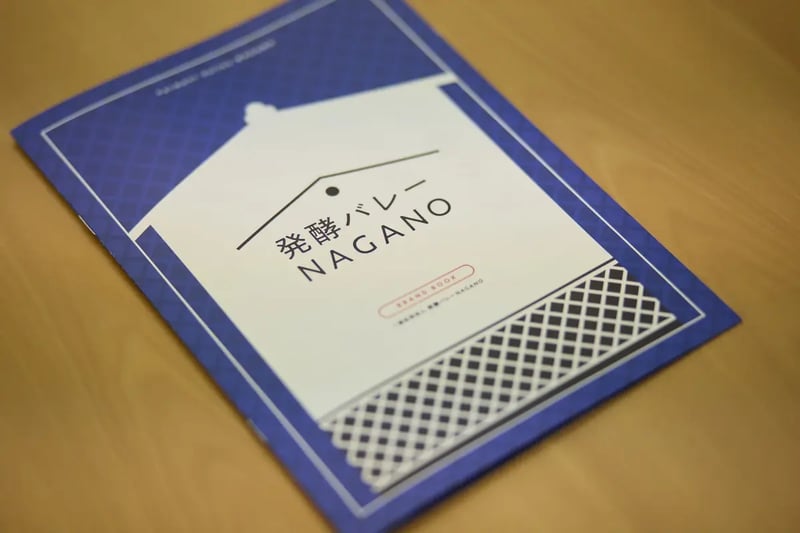
はじまったばかりの「発酵バレーNAGANO」

ご縁がつながり、軽井沢マリオットホテルの長期滞在者向けに体験や学びの機会を提供

軽井沢町から新潟県妙高市までをつなぐしなの鉄道の観光列車「ろくもん」。車両を活用したイベントなど、発酵を軸に地域と融合した企画パッケージを作っている
今は信州大学の国際学科イノベーションセンター内に事務局を設け、発酵業界に横串を刺すことでノウハウをシェアしたり、それらをもとに新しい企画や商品開発に取り組んだりしています。
青木さん「一番は『ミライクリエイター』という名称で、次世代を担うみなさんが参画してくれたのが嬉しいですね。既存の団体ではなかなか一緒に活動することがなかった若い世代が、自分たちのクリエイティビティを発揮して活躍できる素地がある、と、期待を持ってくれた。これからの経営を担う人たちでもありますから、業界がどうあるべきか常に考えているわけで、そういう立場の人同士が問題を共有したり、県や国と話をする機会が生まれた。モチベーションを高めるきっかけにもなっていると思います」

育まれてきた発酵文化、その魅力とは?
ここで改めて、長野県の発酵の歴史にも触れておきましょう。例えば「信州味噌」。これは団体登録商標のひとつで、今ではブランドが確立され、長野県を代表する発酵食として愛されています。はじまりは終戦直後、まだ食糧のほとんどが配給で賄われていた時代に遡ります。
青木さん「食べるものが少なく、自由な商売はできない時代。当時は米もほとんど手に入らず、味噌の主原料となる大豆の仕入れもままならない状況でした。東京では、とうもろこしや芋で作った紛い物の味噌のようなものまで流通していたと聞いています。長野県で商売をしていた先代たちは、間違いない味噌を自分たちがお客様に届けないといけないと考えはじめたんですね」
それぞれ小さな商売をしていたのでは、原材料を仕入れることは難しい。知恵を出し合った結果、組合を作ってある程度のロット数を確保し、共同で仕入れを行うというアイディアが生まれました。また「この味噌は本物だ」と伝えるためには、それに相応しいブランドも必要です。そこで地域ごとに組合を作った上で、さらに県域をカバーする連合会を組織し、団体登録商標を取得しようと方向性が定まっていきました。
青木さん「こうして立ち上がった信州味噌は、まず、紛い物は一切出さないということを決めました。そのために県と一緒に条例を作り、研究所も作って、合格品だと証明できるものだけを樽に詰めて出荷するというルールを作ったんです。本物の米や大豆でできた信州味噌は『とても美味しい』と評判になり広がって、名実ともにブランドが確立されていきました」

信州みそはさっぱりした旨味と豊かな香りが特徴の山吹色。自分たちで高いハードルを設けてそれを全部クリアしたものだけを発信してきた(提供:長野県農政部)

「今でいうところのマーケティングやブランディングを先行して行っていたのは本当にすごい」と青木さん
青木さん「私は、はじまったばかりの発酵バレーNAGANOのあるべき姿も、この信州味噌の歴史にあると思っています。先人たちの知恵と成功事例のように、今は、個々の力を結集するからこそ起こる化学反応みたいなものにとても期待しています」

https://hakkou-valley.nagano.jp/
発酵の伝え手・インタープリターに聞く「発酵旅」のススメ
「発酵」をきっかけにさまざまな取り組みがはじまっていくなか、長野県では「発酵食品×ツーリズム」をけん引する存在として、発酵の伝え手・インタープリターの養成を行っています。今回お話を伺ったのは、須坂市でインタープリターとして活動する信州須坂観光協会の清水智美(しみず・さとみ)さんです。
清水さん「養成のための研修がはじまるということで、せっかくの機会だと思い手を挙げました。研修は全部で4回ほど。これまでも須坂市に観光に来るお客様などの案内はしていましたが、より深い知識を得られそうだという期待もありました」

すでに発酵のスペシャリストとして活躍する各業界の講師を迎えて行われた研修では、長野市にある「西之門 よしのや」や、上田市の酒蔵、高山村のワイナリー、須坂市の味噌蔵などを訪問し、見学や試飲などの体験を通じて学びを深めていきました。
清水さん「インバウンドの方も想定し、どのように発酵文化を伝えていくのか。私たちのような観光協会のスタッフ、市町村の関係者、協力隊など、多くの人が集まっていました。個人的に印象に残っているのは、上田市にある原さんに会えたことです。学生向けプログラムの発酵大学など、具体的な事例はとても勉強になりました」
清水さんのいる須坂市は、松本市や上田市と同じ城下町ですが、規模は一万石ほどと小規模なのが特徴です。しかし、小さいながら今も味噌蔵や日本酒蔵が残り、100年以上の歴史を持つ店もあります。

明治時代は製糸業が盛んだった須坂。市内の繭蔵が残っているエリアを中心に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている

趣ある町並みが残るのは、旧北国街道の脇筋である谷街道。住民からの強い要望を受けて都市計画による道路の拡張工事を取りやめ、街並みを保存してきた

「ぼたもち積み」と呼ばれる建物の基礎部分の石積み技法や、隣地との境界を跨いで設けられた「脇門」などが残る
市内に4つある味噌蔵は、信州味噌をベースに地元産の大豆を使っている蔵が多く、塩はそれぞれに異なり、味や風味の違いを活かした商品開発が進んでいます。
清水さん「2025年からは、須坂市の味噌を使った味噌ラーメンの販売がはじまりました。これまで特徴的な商品がなかったので、何年か前からみなさんと一緒に考えていて、やっと形になった一品です」

シンプルに味噌のおいしさが感じられるように工夫したというラーメン

オリジナルの七味唐辛子や味噌を使った飴「みそ手毬」なども販売されている

清水さんたちはすでにリニューアルも考えていて、「次は須坂市内にある製麺所の麺で第二弾を作りたい」と意気込む
清水さん「味噌蔵や日本酒のほか、今はクラフトビールやワインの醸造も市内で行われるようになりました。私たちも『発酵のまち』としてポスターを作ってPRしたり散策ツアーを企画したりしていますが、改めてこの街のインタープリターとして発酵の歴史や文化を伝え、多くの人に楽しんでもらいたいと感じています」
須坂市、東御市で発酵文化を浴びるスポットを紹介
アトリエ・ド・フロマージュ(東御市)

1982年にはじまったチーズ工房、アトリエ・ド・フロマージュ。2025年1月にレストランやカフェがリニューアルし、抜群の眺望とチーズを使った軽食やスイーツが一層楽しめる場所になりました。お話を伺ったのは、チーズ製造・熟成責任者の塩川和史(しおがわ・かずし)さんです。
塩川さん「フレッシュタイプや白カビタイプ、ウォッシュ、青カビ、モッツァレラなど、6種類くらいのカテゴリーでチーズを作っています。味噌漬けのチーズなど日本独自の味を追求したものもあり、店頭には15種類くらいが並んでいます」

おいしいチーズを作り続けるため、後継者の育成にも力を入れていきたいと話す塩川さん

チーズやチーズケーキ、ソフトクリームの他、屋外にあるテイクアウトのカフェでは八千穂高原にある「きたやつハム」のソーセージを使ったホットドッグの販売も

店内には、長野県産から海外のものまで、チーズに合わせて楽しめるワインがずらり。無料試飲会なども開催される
チーズの味わいを決めるポイントは、原料となる牛乳の質。含まれる脂肪分が多いほど濃厚でリッチな味わいになります。
塩川さん「工房の創業当時は、この辺りも冷涼な気候で、リッチな味わいのチーズを作るのに適した牛乳が手に入りやすかった。ただ最近は気温が高くなっていますから、そうした気候に合わせた工夫が必要です。私たちは“手に入るミルクのポテンシャルを活かし切る作り方”を大事にしています。今はホルスタインとジャージー、そこにブラウンスイスという3種類の牛の生乳をブレンドして、味を追求しています」
発酵という視点で見ると、チーズに必要なのは乳酸菌。気温が低くなる冬は、菌の量を増やしたり生乳の温度を上げてあげたり、菌が働きやすい環境を作ってあげることが大切です。

“ワールドチーズアワード2021スーパーゴールド”でベスト16を受賞したブルーチーズ「翡翠」をはじめ、おいしそうなチーズが並ぶ

カビの付くスピードは季節によって変わるため、常時細かな調整を繰り返す。チーズ工房はガラス越しに見学ができる

「日々同じ作業をしていても、相手にしている菌がどんどん変わるから毎日飽きない」と塩川さん。これからもワールドチャンピオンを目指して進み続ける
塩川さん「チーズって、おつまみや軽食として単体で食べるだけではなくて、調味料としても優秀で。特に醤油や味噌などの発酵食品とは、特有の香りや旨みが融合してくれるイメージがあります。ブルーチーズは生クリームに溶かしてパスタソースにしたり、はちみつと一緒にトーストやピザにのせたり。組み合わせ次第でいくらでも味のバリエーションが広がっていくので、ぜひ試してみてもらいたいです」
アトリエ・ド・フロマージュ
HP:https://www.a-fromage.co.jp/
【森のチーズテラス ショップ】
住所:東御市新張682-2
営業時間:10:00~17:30
定休日:木曜
【森のチーズテラス レストラン】
住所:東御市新張504-6
営業時間:10:00~17:30(L.O.食事/14:00、デザート・ドリンク/17:00)
定休日:木曜

塩屋醸造(須坂市)

江戸後期に塩問屋として創業し、文化・文政年間(1804〜30)から味噌や醤油の醸造をはじめたという塩屋醸造。お話を伺ったのは、11代目となる上原太郎(うえはら・たろう)さんです。
上原さん「海のない長野県で、塩を大切に加工・保存するために味噌や醤油の醸造もはじまりました。湿気が少なく、寒暖の差が激しい気候のおかげで天然醸造ができていますし、創業以来ずっと『風土を醸す』という心を第一にサービスを展開しています」
現存するなかで最も古い蔵は、創業時の江戸末期に建てられたもの。壁が黒ずんで見えるのは、蔵に独自の麹菌が棲み着いている証拠です。

味噌や醤油の醸造だけでなく、街の歴史や地域活動など、さまざまな方面に明るい上原さん

味噌蔵は天井を高く取り、樽を置く下の方が涼しくなるように建てられている

現在は味噌や醤油、漬物、甘酒などを醸造、販売している
上原さん「歴史を遡ってみると、味噌は戦国時代に戦さの携帯食として重宝されていたのがわかります。仙台や愛知、新潟など、強い戦国大名がいるところには大抵良い味噌がある。長野県は、武田信玄が川中島で合戦をする際に味噌を現地調達するため、奨励金を出して、味噌作りの技術を伝えたといわれています」
味噌醸造に適した気候や土地を持つ長野県では、戦さが終わっても味噌作りの技術が残り、農家を中心に自家製の味噌が盛んになりました。「みんなが家で味噌を仕込むので、江戸末期の味噌屋は商売にならなかった」と話す上原さん。しかし明治時代になると、須坂市では製糸業が発展します。生糸を取る工場で働く人が増えるにつれ、醤油や味噌を店で買うという文化が育ってきました。
上原さん「基本的に加工食品の中で味噌って作るのは簡単で必需品、だから自家製だったんです。商売になるかどうかは味次第。味噌用の麹菌にもいろいろなタイプがあって、ふんわり柔らかい感じのとか、ちょっと扱いにコツがいるジャジャ馬みたいなのとか。目には見えないけれど、生き物なので、それぞれに個性がありますね。彼らに伝わっているかはわかりませんが、こちらが愛情深く接すると、やっぱり味が良くなっている感じがします」

かつて使われていた樽と、当時のチョークのメモ書き

塩問屋として食のインフラを支えてきた歴史が残る

蔵の一部はレンタルスペースとして貸し出している。醸造蔵は予約制で見学が可能だ
上原さん「まずは良いものを作るのが大前提ですが、蔵や設備をはじめ、うちには古いモノや須坂ゆかりのモノがたくさん残っています。それらをどんどん活用してもらって、歴史や文化の発信もしていきたいですね。大切にしている『風土を醸す』という言葉には、ここに人が集まって、発酵や地域のこと、歴史や未来を語り合って関係性を醸していくことも含まれています」
塩屋醸造
住所:須坂市大字須坂537番地
営業時間:9:00~18:00
定休日:不定休(基本的には1月1日のみ)
HP:http://www.shioya.co.jp/

発酵からはじまる「おいしい」は日本の誇り
発酵を軸に県内各地ではじまるさまざまな取り組み。改めて「発酵」とはなんなのか、冒頭に登場いただいた青木さんに聞きました。
青木さん「今、世界中から著名なシェフが集うCulinary Institute of Americaという料理の専門学校で、発酵や味噌、麹の特別授業が定期的に行われています。三つ星を狙うようなレストランのシェフたちが聴講に来るんですね。そこで『日本の調味料は、すべて麹からできている』という話をすると、みんなとても驚くんです」

私たち日本人にとっては当たり前の味噌や醤油、甘酒など麹から生まれる発酵食品。それらは日本の唯一無二の文化であり、しっかり発信していくことで、世界中からリスペクトされる可能性を秘めています。
青木さん「発酵は日本の誇りそのものだと感じています。伝えるときに大切にしているのは、やっぱりおもてなしの心ですね。琴線に触れるような物語や気配り。これからも本物のおもてなしをもって、長野県の発酵文化、そのおいしさを伝えていきます」
Event
発酵リトリート旅「Fermenting Peace Stay」
期間:2025年10月18日(土)、10月25日(土)、11月8日(土)、11月15日(土)の全4回
詳細:https://www.karuizawa-marriott.com/rooms/fermenting-peace/
構成:フィールドデザイン 取材・文:間藤まりの 撮影:岡本 浩太郎
閲覧に基づくおすすめ記事