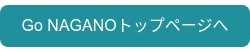先駆者たちが語る、長野県の魅力を掘り起こす新たな旅「テロワール・ツーリズム」座談会
ワインは土地を表現する。だから、その土地を訪ねてこそ得られるものがある。ワインを観光資源のひとつに据えて、長野県の豊かな自然を感じる「テロワール・ツーリズム」。それぞれの立場から新たな旅のあり方について語り合いました。
会場協力|Vino della Gatta SAKAKI(ヴィーノ・デッラ・ガッタ、坂城町)

パネラー(右から)
花岡 純也|長野県観光機構 酒類販売担当、(信州ワインバレー構想2.0推進協議会副会長、長野県ワイン協会アンバサダー)
成澤 篤人|信州ワインバレー構想推進協議会会長、(長野県ワイン協会理事、坂城葡萄酒醸造CEO)
春日 薫|高山村ワインぶどう研究会副会長・ツーリズム担当、(Reve de Vin代表)
清水 良子|長野県観光機構 観光地域づくり担当
「ワインが表現する地」へ来てもらうために
――まず、この座談会の主旨を説明していただけますか。
清水|私たち長野県観光機構は、観光を切り口にした地域づくりやインバウンド誘致、長野県の観光サイトや銀座NAGANOの運営のほか、長野県の観光にまつわるさまざまな事業に取り組んでいます。
その一環として、昨年からワインや発酵食から地域を知る旅の創出に力を入れています。それを「テロワール・ツーリズム(仮)」と名づけました。テロワールとは何か。どんなツーリズムが可能か。この座談会でみなさんの意見をお聞きしたいと思います。

――花岡さんは長らくNAGANO WINEの振興に取り組んできました。ワインと観光について、どうお考えですか?
花岡|僕は長野県観光機構の業務に携わる以前、成澤さんとはお互いに飲食店をやっていた頃から一緒にNAGANO WINE応援団として活動してきました。これは2013年に長野県が策定した信州ワインバレー構想のプロモーションを担う組織です。
当時からワイナリーは増え続け、2025年で90を超える勢いです。長野県のワイン産業は成長して、NAGANO WINEはたくさんの方に飲んでいただけるようになりました。
これまでワインは物産品という扱いをされることが多かったんですが、信州ワインバレー構想推進協議会の初代会長でヴィラデスト・ワイナリーの玉村豊男さんがおっしゃるように「ワインは土地を表現するもの」です。
NAGANO WINEは長野に来て、ブドウが育つ自然環境を肌で感じ、その土地のものを食べながら飲んでいただきたい。その過程をツーリズムにしていく。それが玉村さんから僕らが受け継いで、2023年からはじまった信州ワインバレー構想2.0の核になっています。
今回のツーリズムは、観光機構のいろんな部署をまたいで、いろんな人の協力を得て取り組んでいます。ワインから観光を振興する環境がようやく整った。そんな思いです。
――このツーリズムは、ワインのある土地に主眼を置いているんですね。
清水|そうですね。ワインの好きな方以外も、ワイン以外の観光資源を目当てにして長野に来ていただき、長野のワインと出会う。そういう流れが生み出せればいいなと考えています。
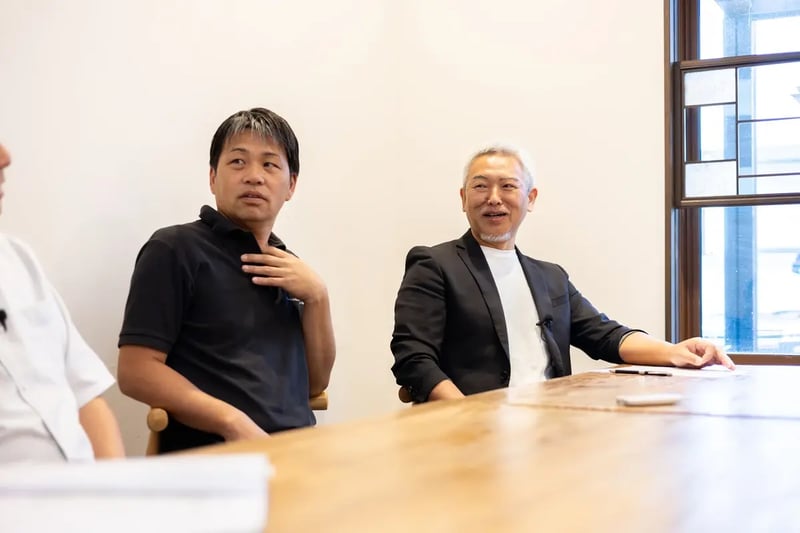
ところでテロワールって何だろう?
――「テロワール・ツーリズム(仮)」という名称は、どうしましょうか。
花岡|わかりやすいのはワイン・ツーリズムという言葉ですが、それだと入口をせばめてしまう。訪れる方に長野の地に親しんでいただきたいからテロワールとつけましたが、より専門的な言葉になってしまうかもしれません。
――テロワールとは、土地を意味する「terre」を語源とするフランス語で、一般的にワイン用語として使われ、ぶどう畑を取り巻く自然環境要因を指す。そんな説明が一般的です
成澤|最近ではワインを語る場面以外でも使われていますね。
春日|高山村も加盟する「日本で最も美しい村」連合を立ち上げたカルビー社長の松尾雅彦さんは生前に「土地の魅力を生かした豊かな農村社会をつくる」という思いを込めて「スマート・テロワール」という言葉を提唱しました。テロワールはワインだけでなく、農村を表す言葉としても使われています。
清水|長野県はテロワールという意味では、すごいポテンシャルを持っています。海外のメディアでも注目されていて、観光機構にも問い合わせがあります。秋にもテロワールというテーマで依頼が来ていて、じつは今日も海外のお客さまをアテンドしています。
花岡|じゃあ安心して(仮)を取りましょう。

ワインは観光資源として強みである
――では改めてテロワール・ツーリズムについて。検証にあたって高山村をモデル地区にしたと聞きました。
花岡|高山村は松川渓谷に沿って源泉のちがう温泉が8つ点在し、それぞれに温泉宿が充実しています。ワイン用ブドウの栽培が盛んで、ワイナリーは6軒ある。こんなに観光資源が集積しているところは、なかなかありません。
――春日さんは高山村ワインぶどう研究会の副会長を務め、ツーリズム担当でもあります。どんなお考えですか?
春日|研究会が設立されたのが2006年。目的はワイン用ブドウの栽培とワイン醸造の技術研究およびワイン文化の振興です。畑の面積は、当初の3ヘクタールから今は67ヘクタール。20倍に広がり、ワイナリーは今年で7軒目ができます。20年間で栽培と醸造に関しては、成果が上がってきています。
高山村は昔から特にシャルドネが良質で、ワイン好きの方には知られているものの、一般的な認知度はまだまだ低い。岐阜県の飛騨高山と混同されがちです。研究会でも村でも、認知向上が課題と考えています。
ワインだけではない土地の魅力、まさにテロワールと、ジビエをはじめとした食を結びつけたツーリズムを推進していくことで、より多くの方を呼び込めるのではないか。そう考えています。
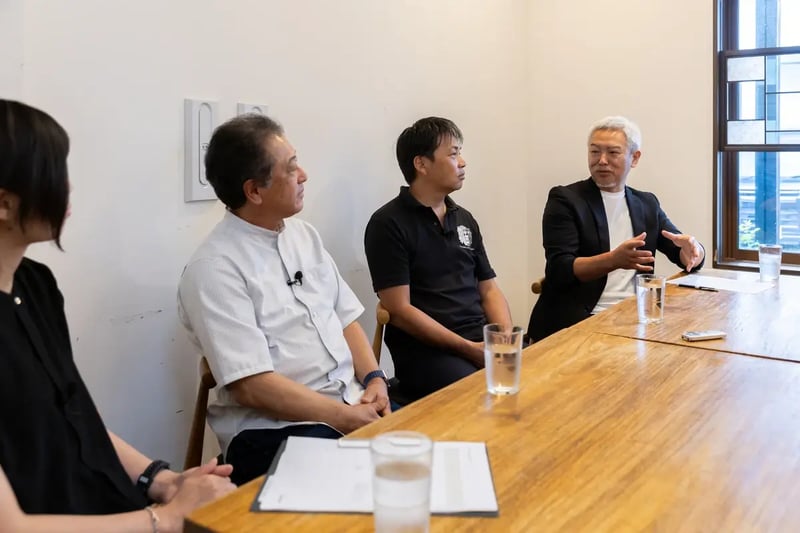
――成澤さんがレストラン併設のワイナリーをかまえる坂城町は、観光資源という点で不利ではないですか?
成澤|確かに坂城町は工業の町で、観光や商業の要素は少ないです。それでもワインをフックにしてできることがあります。毎年5月下旬に「坂城駅前葡萄酒祭」を開催して、人口が約1万2000人の町に、1日で2000人ほどが来場します。塩尻や東御のワインフェスタに並ぶほどの集客です。
高山村の強みである温泉、景観、食。これって全国どこの観光地にもある。でも、ワインを自慢できるところはわずかです。ワインは強みになる。だから高山村は唯一無二なんです。
坂城駅前葡萄酒祭は、ワインだけでなく、おいしいものが食べられることが特徴です。予約の取れないレストランや人気のラーメン店が出店するだけでなく、生ハムやチーズなどの特産品も並びます。
いつもはビールや日本酒を飲む人も、このイベントではワインを飲んでくれます。イベントは打ち上げ花火的なものではありますが、まずは底辺を広げたいという思いでやっています。
――ワインと食を合わせて発信しているんですね。
花岡|成澤さんのワイナリーは収穫ボランティアにも、おいしいごはんが出ます。
成澤|シェフのまかない弁当をお出ししています。レストランがあるのは、うちの強みです。

収穫ボランティアもツーリズム化する仕組み
――収穫といえば、それぞれのワイナリーで工夫してボランティアを募っていますね。
成澤|小さなワイナリーは、なかなか予算が取れず、みなさん収穫のために自腹で来て、無償で働いて、日帰りする方がほとんど。せっかく来てくださる方へのお返しを考えて、2024年から千曲川ワインバレー特区連絡協議会で取り組みはじめたのが「千曲川ワインゴーランド」です。
公式LINEアカウントと友だちになって、千曲川ワインバレー東地区のワイナリーの収穫ボランティアに参加したり、飲食店に立ち寄ると、ポイントが付与されます。ポイントを貯めると、ワインが当たる抽選に応募できます。
LINEでワイナリーそれぞれの収穫日が知らされるので、お客さまは都合に合わせて参加できるし、ワイナリーはファンを共有することができます。
春日|日帰りできるのは利点だと思うんですよ。最近は大人数のツアーではなくて、2人からせいぜい8人くらいで気軽な旅をしている。少人数でも来やすい仕組みづくりは必要だと思います。

――高山村でも取り組まれている?
春日|はい。私のぶどう畑では、昨年は9月初旬から10月末まで収穫が続き、ほぼ毎週8人から10人くらいの方がお手伝いに来られ、東京を中心にのべ100人近くの方に参加していただきました。
高山村は食事を提供できるワイナリーがないんですよ。成澤さんのところとは反対に、食がネックになっていました。
2年ほど前にカンティーナ・リエゾーがラウンジを設けたので、そこで収穫後のランチとワインを軽く1杯召し上がっていただき、収穫後には生ハム工房へお連れしてから日帰り温泉にご案内しました。
とても好評だったので、今年はさらに広げようと、観光機構と一緒に6月に東京で「高山村ワインツーリズム ワイン・食・温泉の魅力を語らう会」を開催しました。
花岡|面白かったのは8つの源泉のお湯を並べたこと。泉質が異なると色も香りもちがうので、見比べたり、匂いを嗅いだりしてもらいました。温泉に興味をもって、高山村へ行ってみたいという方もいました。
春日|ただ、うちもそうですが規模の小さなところばかりなので、ワイナリーやヴィンヤードがどこも受け入れられるわけではないのが現状です。
清水|ツーリズムを検討するなかで見えてきた課題が、受け入れ体制です。

その地を案内してくれるワインガイド
成澤|春日さんがおっしゃったように、長野県のぶどう農家もワイナリーも家族で営む小さなところが多いので、受け入れが難しいんです。
お客さまにしてみれば収穫期にこそ訪れたいけど、受け入れ側は手一杯ということもある。唯一、受け入れ側が来てもらって助かるのが収穫ボランティアです。
――なるほど。ボランティアを受け入れる仕組みが「千曲川ワインゴーランド」ですね。では、ツーリズムのお客さまはどうしましょう。
花岡|収穫期に来ていただけないと、ブドウが実るいい景色も見ていただけない。それでは販売機会の損失につながります。そこではじめたのが、ワインガイドの育成です。
これは信州ワインバレー構想2.0に掲げるインタープリター(interpreter)という人材、いわば伝え手です。ワインバレーごとにワインガイドを設置して、ワイナリーに代わってお客さまを案内します。
――ワインガイドになるのは、どういう人たちですか?
花岡|ワイナリーの信頼のうえに成り立つ仕組みなので、ワイナリーにヒアリングして、複数から名前の挙がった方に声をかけました。お客さまをワイナリーへ案内したり、すでにご自身でガイド的な動きをしている人たちです。
お客さまはワインのことだけでなく、山の名前や、おすすめの飲食店も聞いてきます。だから地域のことをよく知る必要がある。ワインに関する知識があることを前提にして、ガイディング技術に重きを置いた育成カリキュラムを組んでいます。
――そんな人たちが活躍してくれたら、心強いですね。
春日|本当にそうですよ。海外ではワインを主体とした地域めぐりをする際に、ガイドの方がワインだけでなく土地のことを含めて面白くお話ししてくれる。それが印象に残るんです。ガイドの魅力は強い発信力になるし、継続的に人を呼び込めるベースになると思います。


テロワール・ツーリズムの可能性
――今後テロワール・ツーリズムでできることは、なんでしょう。
花岡|地方創生や観光の勉強をしている大学生に、研究の一環でプランを考えてもらったんですが、印象的だったのは、ぶどう畑でのガーデンパーティ―という案。どうやら人気のYouTuberが海外のワイナリーで結婚式を挙げて、それが話題になったらしいんです。
現状でワイナリー主催のツアーに来る人は60歳以上でリピーターが8割です。ツアーの内容は、ぶどう畑や醸造施設を見学して、醸造家に解説してもらいながら試飲をするのが基本。参加するのは、それを時間のある限り何軒も回りたいという人たちで、自分たちで行程を組んで来るという一番コアな層です。
ライト層だと、犬や子どもを連れて、ぶどう畑でご飯を食べたいという方たちもいる。ワインではなく、畑の美しさに価値を感じているんですね。
春日|確かに、景観は価値のひとつです。私が一番好きなのは冬なんですよ。一面の雪に覆われて、きれいな空気の中、冠雪した北アルプスが遠くにきれいに見える。その風景の中で剪定作業をする幸せを、ぜひ味わっていただきたいです。
花岡|そのあとの温泉なんて最高でしょうね。収穫以外にも年間を通して体験できることがある。
学生たちにぶどう畑で芽かき作業をしてもらったんですが「いいブドウを作るために、こんな作業があることを知って感動した」という感想を聞けました。

――テロワールには人の技術や哲学も含まれる、そう明言する人もいます。
花岡|そのとおりで、気候や土壌がテロワールとして語られがちだけど、同じ畑のブドウでも手がける人が変われば、まったくちがうワインになる。テロワールへの人の関わりはものすごく大きいと思います。
成澤|長野県のワイン用ぶどう畑の多くは遊休農地を活用しているので、そもそも人の手で開墾しています。新規就農や移住者が多く、僕も含めて創業者って、その土地への思い入れが強い。僕は生まれ故郷なので、なおさらです。
春日|みなさん個性豊かで、そんな方たちの話を聞くだけでも面白いですね。一方で農業を担う多くはお年寄り。そんなシリアスな現状も感じ取っていただきたいです。
清水|なぜ収穫ボランティアに人が集まるのかといえば、やはりワインづくりに携わる人たちが魅力的だから。その背後にある暮らしを体験してみたいというニーズがあることを肌で感じています。そして、その地に住む人だけでなく、訪れる人もまたテロワールに関与しているのだと思います。
花岡|僕らが長野県ならではのテロワールを広く掘り起こし、発信していけばいいんだと自信がもてました。
――ワインのある土地や関わる人もまとめて楽しむテロワール・ツーリズムのこれからに目が離せません。みなさん、ありがとうございました。
構成:フィールドデザイン 取材・文:塚田 結子(編集室いとぐち) 撮影:荒井 康太
閲覧に基づくおすすめ記事