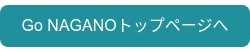伝統と住民の思いが息づく、水の宿場「須原宿」
中山道六十九次、三十九番目の宿場である「須原宿」。六十九次の中では最も新しい年代に建築され、木曽路を行き交う旅人や物資の中継地として大いににぎわったといわれている。この宿場町に残る江戸の面影や静謐な空気感を写真家・宮崎純一が写し取る。

須原宿の町並みを歩くと、通り沿いで静かに水を湛える「水舟」が目に入る。江戸時代から受け継がれてきた生活水の文化で、かつては井戸水を使った水場が十数軒単位で整備されていたという。上下水道の普及により一度は姿を消したが、地域の手によって復興され、今も住民たちの手で丁寧に守られ、暮らしのなかに息づいている。




勝野さん夫妻に教わる、須原宿の歩き方
須原宿を案内してくれたのは、本通りで鍼灸院を営んでいる勝野さんご夫妻。
ご主人の誠吾さんは須原宿出身で、須原宿景観形成住民協定運営委員会の会長のほか、依頼があれば須原宿を案内するガイドも務めている。奥さまである清子さんは婦人会、須原ばねそ保存会の副会長をはじめ、子どもたちの育成指導、保護司なども務める、いうなれば“須原宿のゴッドマザー”的な存在だ。須原宿について知りたいなら、この二人に聞けば間違いない。

1959年9月の伊勢湾台風では、木曽地域も大きな被害を受けた。
「私が中学生のころでした。石屋根が次々と飛ばされて、町並みの一部が壊れてしまったんです」。伊勢湾台風は宿場町の歴史的な風情にも深い傷跡を残したという。また、妻籠宿や奈良井宿に比べると、町並み保存への取り組みが始まったのがやや遅かったため、江戸時代の面影に昭和期の商店や住宅が入り混じった景観になったのだという。
「伝統的建造物群保存地区には指定されなかったのですが、かえって『新旧ある町並みがおもしろい』とおっしゃる観光客も多いんですよ」と誠吾さん。確かに、江戸時代の面影に、時代の異なる店舗や住まいが混在している風景は味わい深い。

須原宿の東側、赤い欄干の橋を渡った先にある「鹿島神社 本宮」にも案内してもらった。創建は768年と伝わる古社で、境内には村の文化財に指定された樹齢約800年の御神木がそびえている。
毎年7月中旬には鹿島神社の本宮から仮宮への遷座を背景にした祭礼「鹿島神社例大祭」が行われ、2日間に渡り町全体が熱気に包まれる。中学生や地域の人々が長い棹(さお)と木箱を担いで宿場を練り歩く「長持ち」や白装束に身を包んだ神輿巡業、地域の伝統芸能「須原ばねそ」という踊りを披露。宿場町の通りに賑やかな掛け声と太鼓の音などが響き渡る。
誇りとともに伝統を継ぎ、地域の絆を今も大切に育む須原宿を歩くほどに、その静かな熱さに心が揺さぶられる。歴史とこの宿場を守り、次世代へ繋いでいく地域の人々の思いに触れながら、もう一度この通りを、今度は少しゆっくり歩いてみたい。


【須原宿】
問い合わせ:0264-55-4566大桑村観光協会
Googleマップ : https://maps.app.goo.gl/ByZBYm9hZzPzU6UN6(須原駅)
人々の営みがそのまま息づく宿場「野尻宿」
江戸時代の面影を残す中山道40番目の宿場町「野尻宿」。馬籠、妻籠、奈良井など名の知れた宿場とは違い、多くの人が訪れる場所でないからこそ静かな散策が叶う場所だ。整えられた景色ではなく、そこに暮らす人々の営みがそのまま息づいているかのような野尻宿の風景を、フォトグラファーの宮崎純一さんが写し出す。

東のはずれから西のはずれまで、東西貫く道の長さは約660メートル。木曽11宿の中では、奈良井宿に次ぐ長さを誇る。野尻宿といえば、曲がりくねった町並み「七曲り」が特徴的だ。江戸時代に外敵の侵入を防ぐために設計されたもので、道が何度も曲がることで視界を遮り、進行を遅らせる構造になっているのだという。かつては敵の侵入を防ぐための構造だったが、今では静けさと余白を生む仕掛けとして宿場の空気を守り紡いでいる。





【野尻宿】
問い合わせ:0264-55-4566大桑村観光協会
Googleマップ : https://maps.app.goo.gl/GF5rtkReopZDv5HJA(野尻駅)
町並みに静かに寄り添う珈琲時間
ひと通り宿場を歩いた後に、気になっていた1軒のカフェに立ち寄ってみた。
元は鍛冶屋だったという築100年の古民家を改装。横浜から移住した犾舘(えんだて)夫妻が6年前にオープンさせた店だ。馬籠や奈良井などといった有名な宿場町とは違い、あまり人が通らないこの静かな場所を選んだ理由は何だったのだろう。
「ふたりともバイクが好きで長野にはよくツーリングで訪れていたんです。奈良井宿には立ち寄ったことがあったのですが、野尻宿のことはまったく知りませんでした」と和(ひとし)さん。県内各地で移住先を探す中で、たまたま訪れたこの建物がひと目で気に入り「帰りの車の中でここに住むことをふたりで決めました」(絵美さん)


元は鍛冶屋だった建物、そしてふたりともバイクが趣味でスズキの「KATANA」というバイクに乗っていたこともあり、店名は「刀(かたな)」に。「バイク好きの方が気軽に立ち寄ってもらえる場所にしたいと思っていたので、むしろ賑やかな観光地じゃない方がよかったんです」と和さん。そういう意味でもこの静かな宿場町はふたりの理想の場所だったのだという。


野尻駅から阿寺渓谷までは歩いて30分ほど。「その道のりがいいんですよ。古き良き、昔の田園風景が残っていて。阿寺渓谷へ行くならぜひ駅から歩いてみてください」と和さん。阿寺渓谷は8月末まで車両通行規制が行われているので一般の車両は進入禁止になる。ゆっくりローカル鉄道に乗って野尻駅で下車。駅から散策しながら歩いて向かうのがお勧めだ。
阿寺渓谷を堪能した後は「珈琲 刀」で休憩し、今秋開業予定のゲストハウスで静かな夜を過ごす。翌日は江戸時代にこの道を行き来していた旅人に思いを馳せながら、ゆっくりと時を刻む野尻宿の町並みを歩いてみる。次はそんな旅を計画してみてはいかがだろうか。
【珈琲 刀】
住所:長野県木曽郡大桑村野尻1724
営業時間:10時~17時30分、金曜~20時
定休日:月曜(祝日の場合は翌火曜)
HP:https://coffeekatana.wixsite.com/cafe
Googleマップ : https://maps.app.goo.gl/jxm1JEZV2r9aBCuG8
撮影:宮崎純一 取材・文:大塚真貴子 イラストマップ:佐藤妃七子
閲覧に基づくおすすめ記事