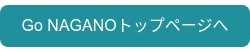南木曽駅から三留野宿までも見どころ多数
三留野宿がある南木曽町は、木曽地方の言葉で「蛇抜(じゃぬけ)」と呼ばれる土石流災害が発生するなど、たびたび土砂災害に悩まされてきた。木曽川に沿って続く中山道も水害などにより通行不能になることがあり、南木曽町の三留野から大桑村の野尻へと峠越えをして移動する与川道は、その迂回路としてできたといわれている。
与川道の全長は約13.5キロメートル。南木曽駅から徒歩で向かうとなるとその距離は約15キロメートル、徒歩で5~6時間ほどかかる。道中には集落や沢、竹林、針葉樹の森など、さまざまな風景が広がり、見どころが多いことも、訪れる人々の心を惹きつけているのだろう。
15キロメートルの道のりには、舗装道路と未舗装の道があり、途中峠越えなどのアップダウンもあるため、スニーカーやトレッキングシューズといった歩きやすい靴で出かけるのがいい。また、与川道には自動販売機や売店などがないので、事前に十分な飲み物や昼食用の食料などを準備しておくのを忘れずに。
道のりは舗装路と山道が交互に続いているが、舗装路でも車はあまり通らず、自然の風景や音に触れながら歩くことができる。しかし、例年、町内ではクマの目撃情報も寄せられているそうなので、鈴など音の出るものを携帯しておくとより安心してハイキングを楽しむことができるだろう。

散策コースの出発点は、JR中央本線の南木曽駅。南木曽駅は1909年、官設鉄道 三留野-坂下間延伸時に開業、100年以上の歴史を持つ。1968年に現在の南木曽駅へと改称した。
南木曽駅から与川道へ向かうルートからは外れるが、駅から徒歩約8分の場所には1994年に国の重要文化財に指定された「桃介橋(ももすけばし)」がある。福沢桃介が水力発電所開発のために架けた吊り橋で、1922年に完成。全長247メートルの木製で補剛トラスを持った吊り橋としては日本最大級の橋のひとつといわれている。
ほかにも南木曽駅周辺には、徒歩で三留野宿を目指す途中に立ち寄りたい名所がいくつかある。「和合の枝垂梅(わごうのしだれうめ)」は、例年3月下旬に見頃を迎える名木で、江戸時代の酒造家・遠山氏が庭木として育てたことから、町の天然記念物に指定されている。また、曹洞宗の古寺「等覚寺(とうがくじ)」には、重厚な鐘桜門や、町指定文化財の円空仏3体(韋駄天像など)が安置され、公開もされている。
与川道の起点となる中山道・三留野宿は江戸から数えて41番目となる宿場町。南木曽駅からは歩いて20~30分ほどだ。
三留野宿は過去に計4回の大火に遭い、1881年の大火ではほとんどの家が消失してしまったことから、江戸時代当時の建物は残っていないが、往年には、徳川家に嫁いだ皇女和宮や明治天皇が三留野宿本陣に宿泊するなど、中山道の中でも主要な宿場町として栄えていた。
現在、宿場の中心には本陣跡、脇本陣跡が残されており、本陣は大火で焼失したものの、その庭木「三留野宿本陣後枝垂梅」は現存。訪れた人の目を楽しませている。



歴史の道・与川道へ。
三留野宿を出発して三留野宿本陣跡を過ぎ、宿場の端にある「吉田木工所」を目印に進むと、中山道の本道へ進むルートと与川道との分岐点にたどり着く。与川道方面を選択し、田園風景を見ながら坂道を上り、「中山道」の案内板の指す方へ山道を進むと「廿三夜塔(にじゅうさんやとう)」が見えてくる。二十三夜の遅い月の出を拝み、豊作などを祈る民族信仰の塔で、遅い月の出を立って待つことから「お立ち待ち」とも呼ばれている。
与川道の途中には、点々と公衆トイレが設置されているが、「上野原トイレ」を過ぎると、しばらくは無いので、ここで立ち寄ってから先へ進むといいだろう。


「廿三夜塔」から舗装道路に出て200mほどのところにグランピング施設「ties Camp Ground Nagiso」の姿が。さらに施設の横を通り、道を進むと三差路の手前に出る。そこから「中山道」方面へ舗装された道を進んでいくと、ゲストハウス「Hostel 結庵」が見えてくる。そしてしばらく歩くと江戸時代に与川村と三留野村の境界とされた「正善沢(しょうぜんさわ)」に到着する。ここからしばらく行くと視界が開け、田園風景や集落など、昔懐かしい風景を眺めることができる。
途中、与川道からは外れる場所ではあるが、死後の世界をつかさどる十人の王が祀られているお堂(実際には十三人の王が祀られているという)「十王堂(じゅうおうどう)」がある。
また、その先には「古典庵 木曽八景 与川の秋月」と呼ばれる小高い丘があり、仲秋の名月をここから眺めると、周囲の地形と調和して見事な景観が広がるといわれている。「古典庵」の名は、かつてこの地に与川氏の菩提寺があり、その寺院名に由来すると伝えられている。
良寛の歌碑「さむしろに 衣がたしき ぬばたまの さ夜ふけ方の 月を見るかも」が建てられており、現在でも毎年集落の人々が集まって、月見の宴を開いているのだそう。


松原御小休所でひと息つき、旅路は折り返し地点へ。
三留野宿を出発して、2時間ほどで「松原御小休所(まつばらおこやすみじょ)」に。高貴な方が通行する際の休憩所として見晴らしの良い場所に建てられた「松原御小休所」も、今は木々が茂り、木陰で休息できる涼やかな場所になっている。
御小休所でしばしの休憩を挟んだあとは、約1キロメートル先にある「阿弥陀堂(あみだどう)」へ向かう。「阿弥陀堂」の境内には、庚申碑・巡礼参拝碑・名号碑などの石碑が多くあり、古いものでは1692年のものもあるという。
※現在、阿弥陀堂手前の、三和自動車上の中山道を進むルートは、土砂崩落のため通行禁止となっているため、案内板に従って迂回路を利用。
https://nagiso.jp/yogawamichi/(開通情報は南木曽観光協会のHPを参照)

阿弥陀堂を過ぎて棚田の脇の道を抜け、竹林の中をしばらく行くと、再び民家の姿が見える開けた場所にたどり着く。里山の風景を眺めながらさらに歩いていくと、江戸時代には欄干を備えた立派な橋があったとされる「らんかん橋」へ到着。

「らんかん橋」を過ぎると、与川道のピーク「根の上峠(ねのうえ峠)」まではもう少し。峠道に差し掛かると道は若干急な上り坂となる。
両側に針葉樹が立つ道をさらに上っていくと、1761年に建立された石仏に「右やまみち、左のぢり道」と刻まれた「石仏道標(せきぶつどうひょう)」の姿が見える。
左の「のぢり道」を進み、ピークに向かう最後の急勾配を上っていくと、かつてここにも御小休所が設けられていたという与川と野尻の境の峠「根の上峠(ねのうえとうげ)」に到着する。


南木曽駅から15キロメートルほどあった道のりも、ピークの「根の上峠」から野尻宿まではあと4キロメートルほど。しかも残りは下り道となるので、自然と歩調も穏やかになりのんびり歩くことができる。
江戸時代に残された史跡と、どこか懐かしさを誘う与川道。非日常を感じられるこの道を、ぜひ歩いてみてほしい。
問い合わせ先: 0264-57-2727南木曽町観光協会、0264-23-1122木曽観光連盟
■与川道MAP
写真提供:木曽観光連盟 MAP:南木曽町観光協会 文:児玉さつき 構成:大塚真貴子
閲覧に基づくおすすめ記事