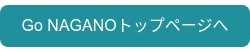寒い地に息づいた凍み同様の郷土食
八ヶ岳山麓に位置した茅野市。冬の厳しい寒さを生かした保存食 “凍み”の食文化が根付く地だ。食材を冬空にさらし一度凍らせてから乾燥させる寒天や凍み豆腐などの製法と同様。寒冷な気候を生かし作られる「寒晒しそば」という幻のそばがあるという。
茅野市に残る文献によると、この地で寒晒しそばが作られ始めたのは江戸時代。1789年、高島藩・第9代藩主の諏訪忠粛(すわただとし)が徳永家将軍に献上したのがはじまりだという。
一度はすたれてしまった寒晒しそばだが、当時の文献を読み解き20年程前に復刻させたのが、そば農家の小林一茶(ひとし)さんだ。
秋に収穫した玄そば(殻が付いた状態)を冬の一番寒い時期とされる“大寒”の日、清流に1週間ほど浸し、約1ヶ月間天日にて自然乾燥させる。そして保存、熟成させたものが寒晒しそばとなる。

諏訪大社で祈願してもらった玄そばを川に沈める。清流に1週間ほど浸すことで雑味が抜けるそう

八ヶ岳蕎麦切りの会、会員のそば店で手分けし、1ヶ月ほどかけて天日干しにさらす。「引き上げた当初は凍っているのでとけてからひっくり返す作業を繰り返します。毎日のことなので、これが一苦労なんですよ」(八ヶ岳蕎麦切りの会 会長の矢野さん)

長野県で栽培されているそばの品種で一番多いといわれる信濃一号。「献上寒晒しそば」もこの品種を使用
文献を紐解き、伝統の技を再現
真冬の冷たい川から引き上げられた玄そばを寒空の下に置く。氷点下の外気にさらされることで自然と凍り、日中の陽光でゆっくりととけていく。表裏を入れ替え、凍るととける作業を繰り返し行う。まさに昔ならの寒天作りと同じ手法だ。
そうして1ヶ月ほど乾燥させると、川から吸い上げた水分が徐々に抜けてくるのだという。
「水分量が16%になるまで乾燥させます。国が定めた一般のそばの水分量が16%なので、そこまで水分を抜くんです。水分が多いと実が蒸れてしまったり、製粉のときに目詰まりをおこしたりトラブルの原因になってしまうので」(髙山製粉・高山さん)。
約1ヶ月かけて乾燥させた玄そばを諏訪市にある高山製粉にて製粉する。
「ふるいにかけ使える実を精査した後、石臼で製粉します。寒晒しそばは通常の玄そばに比べると工程が多いので、製品になるのはほんの6割ほどなんですよ」
昔は夏まで玄そばの状態のまま土蔵や氷室などで保存していたそうだが、現在は品質維持のため製粉してからマイナス30度の冷凍庫で保管する。そして夏の土用を前に八ヶ岳そば切りの会各店舗へと納品される。

2025年に提供する「献上寒晒しそば」のそば粉。清流にさらすことで新そば特有の緑がかった色より、若干色味が薄くなるという

株式会社髙山製粉・工場長の髙山さん。復刻当時から寒晒しそばに携わっている

株式会社高山製粉(諏訪市中洲465-3)石臼挽き製法にこだわり創業100年以上の歴史をもつ。そば打ち体験もできる(要予約)
風土を生かした先人たちの知恵の結晶
寒晒しそばは、冷蔵庫のなかった時代、夏でもおいしくそばを食べるために編み出された食の技だ。
「そばはお米と違って殻が柔らかく、タンパク質が多いので虫の被害に遭いやすいんです。そのため、川の水に漬けてタンパク質を水に流してしまうんです」、教えてくれたのは八ヶ岳そば切りの会・会長である矢野さん。呉竹房の店主でもある。
「そばは生きているので、タンパク質がなくなったら今度はデンプン質をどんどん増やしはじめるんです。そうしてデンプンが多い甘いそばになるんです」 清流に浸す工程にそんな理由もあったとは、まさに気候風土がもたらす知恵の産物。先人たちがそこまで見越してこの工程を編み出したのかと思うと頭が下がる思いだ。

呉竹房店主・矢野さん。東京のそば店で修行し地元にて開業。2025年より八ヶ岳蕎麦切りの会・会長に就任

寒晒しそばは、夏に食べるものがなく編み出されたという保存食。真夏でも「うまいそばが食べたい」という将軍の願いを叶えるため、幕府に献上されたのだという
「以前はウチでも普通に出していたんですが、『普通のそばと味がかわらないじゃないか』という方がいたので、食べ比べができる2種盛りを出すようにしたんです。すると『やっぱり違うね』って言っていただけるようになりました」(矢野さん)
通常の十割そばに比べると、甘さが際立ち、モチモチした食感も特徴だという。
「食べ比べてみていただければわかると思うんですが、食感が全然違うんですよ。あとは風味ですね、寒晒しそばは雑味が抜けるので、普通の十割そばに比べて『お上品だ』っていう人もいるし、逆に『物足りない』っていう人もいて、感じ方は人それぞれなのがおもしろいですね」
矢野さんのお店のように食べ比べできる店もあれば、そばの香りや甘みをダイレクトに感じてほしいと、水そばを付けて提供する店もある。

7月18日~八ヶ岳蕎麦切りの会5店にて提供
2025年現在「献上寒晒しそば」を味わうことができるのは、八ヶ岳蕎麦切りの会5店舗のみ。時期は7月18日(金)~7月末の予定だ。各店、数が限られているので、そばが終わり次第終了する。
「すべて手作業なので量をそんなに作れないんです。毎年楽しみにしている人もいるので、もっとたくさん作れたらいいのですが……」(矢野さん)
復刻当初は13軒ほど加盟していた会も、現在はわずか5軒になってしまったそう。確店限定数の提供だが、7月最終週、また状況によっては8月に入ってからも残数次第では提供できる可能性もあるというので、事前に確認してから出かけるのがいいだろう。
今の時期のみ、限られた店でしか味わえない、まさに“幻のそば”、この機会にぜひ味わってみてはいかがだろう。
①信州手打ちそば工房 遊楽庵
国産の玄そばと横谷峡の湧き水を使った十割そばは、挽きたて・打ちたて・茹でたての三拍子がそろう本格派。つなぎを使わないそば本来の風味が楽しめる。そば打ちの見学や体験もでき、売店では地元の特産品やそば関連の商品も販売する。

②手打ちそば処 やまなみ
「道の駅 ビーナスライン蓼科湖」から徒歩すぐの場所にあるそば処。店内の窓からは、店名の由来にもなっている八ヶ岳連峰の雄大な山並みを望むことができる。地元産のそば粉、水は蓼科山の伏流水を使用し、素材が生きたそばが味わえる。

③本格手打ちそば 味処 長寿更科
ビーナスライン沿い、八ヶ岳の山並み望める同店で味わうそばは、丹精込めて育てられた八ヶ岳山麓産の玄そばを使用。つなぎを一切使わず、そば粉だけで打つ十割そばは素材本来の風味と力強さを存分に味わえる。

④手打ちそばの呉竹房
そば切り発祥の地・東京で修業を積んだ店主が打つ10割そばが楽しめる店。信州産の厳選そば粉を店内の石臼で丁寧に自家製粉。挽きたての香りをそのままに手打ちで仕上げる本格そばが昼夜味わえる。

⑤信州本手打そば 勝山そば店
日帰り温泉施設「金鶏の湯」目の前にあるそば店。八ヶ岳山麓で育ったそばを厳選し鬼殻ごと挽いたそば粉を、お湯打ち・足踏み製法で仕上げている。力強く濃厚な田舎そばは素朴でどこか懐かしい味わい。

撮影/宮崎純一 取材・文/大塚真貴子
閲覧に基づくおすすめ記事