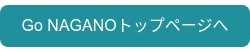「アート(芸術)」と「ドッグ(犬)」が同居する至福のデザインホテル──『ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA』
第Ⅰ章 森の中のホテルへ──静けさと光のあいだに

北側全面が窓となり四季折々の採光がメインロビーを彩る。大小のソファとテーブルは犬と人の移動を考慮した配置に。この開放感がとても心地良い

エントランスロビーにも『EIJI TAMURA』氏の作品が。当施設がドッグフレンドリーであることを物語っている
軽井沢の朝は、どこか時間の流れがゆるやかだ。霧を含んだ空気が木々の間を抜け、鳥の声が遠くでこだまする。私はその道を進みながら、一棟のホテルを目指していた。犬と人、そしてアートが同じ空間で呼吸する場所──「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」。
建物に足を踏み入れると、エントランス右壁面にカラフル&ポップな色彩とデザインで描かれたアートに目が奪われる。日本、ニューヨークを拠点に活動するドッグアートアーティスト=「EIJI TAMURA」氏によるクリエーションだ。その正面、もう一つの作品がコレクションされたフロント前にオーナー=神谷正樹さんが立っている。
ロビーメインランウンジへ進む。まず感じるのは"静けさのデザイン"だ。巨大な暖炉と壁面ガラスが互いを侵さずに調和し、大きな窓の向こうには軽井沢の風景が広がる。そこには犬と人が同じソファでくつろぐ姿があった。それは観光地の賑わいとは対極にある、軽井沢が本来もつ"余白の美"そのものだった。
「もともとここは、私たちが自分たちの愛犬と安心して泊まれる宿を探したことがきっかけでした」と、穏やかに語り始める。信州で暮らすようになって二十数年。この町は「別荘地」ではなく「日常」になっていた。「犬を飼っていると、旅の選択肢が限られますよね。"ペット同伴可"と書かれていても、実際は気を使うことが多い。だから、自分たちが気兼ねなく泊まれる宿をつくろうと思いました」。
軽井沢という土地の持つ静謐さと、犬と共に過ごす時間の穏やかさ。それらを両立させるには、派手なリゾートではなく"空間の質"が必要だった。日々、建築材料を探求し「犬がいても美しく保てるデザイン」を徹底的に考えた。素材はすべて本物。無垢材、そして自然光を最大限に取り込む構造。それらが調和して初めて、犬と人が同じ居場所に立てる。「犬を中心に考えたとき、結局"人間の快適さ"も見えてきます」と微笑む。

たとえば床は、犬が滑らず清潔を保てるだけでなく、人が素足で歩いたときに心地よい温度を感じる素材を選んだ。「犬のため」がそのまま「人のため」にもなる。このホテルの哲学は、そんな循環にある。
軽井沢の季節は、光の角度で表情を変える。春は芽吹きの緑、夏は濃密な影、秋は黄金色の風。「この町にとって"建物"は、自然の延長線上にあります」。その言葉はどこか詩のようだった。
オープン当初、客層の多くは犬連れの家族や夫婦。だが近年は、アートやデザインを目的に訪れる人も増えているという。「結果的に、犬が"このホテルの一員"として存在してくれています。犬がいるからこそ、空気が柔らかくなる。人だけの空間にはない、優しいリズムが生まれていきます」。その言葉を聞きながら窓の外に目を向ける。テラスで、犬がゆっくりと風を嗅いでいる。その隣で飼い主がコーヒーを飲み、ふと目を合わせて微笑み合う──。その何気ない一瞬こそが、このホテルが目指す「共生のかたち」なのかもしれない。
第Ⅱ章 アートと空間──"共感"をデザインする

ランドマーク的存在感を醸す吊り下げ式暖炉。質の高い音響設備と壁面のアート作品コラージュ。時間の経過を忘れ、時の流れの中に滞在する

一面を構成するアートとブックライブラリー。蔵書は犬と旅関連をセレクト。ロビーのソファに腰を下ろし「犬文学」が楽しめる。コーヒーなどのオーダーも可能だ

エントランス脇の階段を上がると2階フロアーに入る。その一角、心和むさりげないアート空間
「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」を歩くと、どこを切り取っても「静けさの中にあるアート」を感じる。それは装飾ではなく、空気の一部として存在している。壁面にかかる絵画も、照明の影に沈むオブジェも、すべてが"主張しない美"として調和していた。
「アートって、特別なものじゃないと思っています」と神谷さんは言う。「日常の中に自然にあって、気づくと心がほどけている。そういう存在でいい」。もともとは出版業に携わっていた。だからこそ、見た目の派手さではなく、"空間に流れる感情の温度"を重視した。
ホテルのアートを選定するにあたり、大切にしたのは「作品と場所の対話」である。有名作家の作品を並べることよりも、軽井沢という土地の光や湿度に合うもの。「作品が空間の中で呼吸できるかどうか。その感覚を、ひとつずつ確かめながら置いていきました」。
館内のアート作品は、時間とともに表情を変える。「昼と夜で全く違う表情になります。朝は冷たさ、夜は暖炉の温もり。同じ作品が、時間で変化する感覚があります」。神谷さんの言葉は、まるで一枚の絵を描くようだった。
さらに、建物全体には"音のデザイン"も施されている。犬の足音が響きすぎないよう床材に微細な吸音処理を施し、廊下の照明は人と犬の視点の高さで柔らかく落ちる。「犬がリラックスできる環境を作ると、人間も落ち着きます。それは、アートと同じ原理です」。
アートの本質は、見ることではなく「感じること」。だからこそ、このホテルでは「展示」ではなく「共感」が設計されている。宿泊者が作品に気づかなくてもいい。ただ、空間の中で何かを感じたとき、それが"アート体験"になっている。
神谷さんは、アーティストとも積極的に交流している。「冬季の閑散期には若手アーティストに客室をアトリエとして無償で長期提供しています。冬の軽井沢はアトリエを構えるにふさわしい静謐な環境……皆それぞれ静かに創作していただく。このホテルを、そうした作家たちの"通り道"のようにしたいと思っていて」。アートの展示は、宿泊者にとっても発見の時間となる。「うちに泊まったお客様が、翌日にその作家さんを訪ねる。そんな循環ができたらいいなと思っています」。
アートは、飾るものでも、語るものでもなく、"関係を生む媒介"としてここにある。神谷さんの声には、ビジネスよりも文化の匂いがあった。「観光って、消費じゃないと思うんですよ。その土地の文化や人と"関係を結ぶ"こと。それを続けていけば、きっと持続可能な軽井沢になる」。
第Ⅲ章 犬と人のウェルビーイング──"滞在"から"暮らし"へ

約35㎡、最高4.2mの吹き抜け。3名まで宿泊可能。アーシーカラーでコーディネートした室内は外光と内部の調光によりさまざまな空間美を奏でる

子どもとともに就寝することを考慮し設置したエキストラベッド。目線の高さに差をもたらすことで安らぎの様子を見守る。低いベッドは大きなベッドの下に収納可能

「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」はコンドミニアム型ホテル。全室にキッチンが備わる。地元食材を使用した調理、長期滞在にも対応。(朝食サービスはあるが、「地域の食事も楽しんでほしい」というオーナーの思いが伝わる)

自然光と森の風を受けながらのバスタイムはヒーリング効果をもたらしてくれそう。

ベランダ付きの客室。気温が高い日、雨の日の滞在へのホスピタリティ。犬たちにとっても良好な居住環境
「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」のロビーでは、宿泊客と犬が、まるで自宅のように過ごしている。ソファの上には読書をする人、床には丸くなった犬。その自然な光景に、誰も違和感を覚えない。
「うちのホテルを"宿泊施設"だとはあまり思っていません」と神谷氏は言う。「むしろ"暮らしを体験する場所"です」。
滞在することで気づくのは、このホテルが"犬中心"でも"人中心"でもないということ。空間の設計も、サービスのあり方も、双方が無理なく共に過ごせるバランスで構築されている。
「犬の存在を"制約"ではなく"要素"として考えるんです。一緒にいることで見える景色がある。それをどうデザインするか、がテーマです」。
たとえば、客室のソファは犬が上っても傷つかない素材を使う。ラウンジのソファの高さは、犬が視線を合わせやすいよう低めに設計されている。「人の視点で考えると些細なことですが、犬にとっては安心感につながる。その安心感が、結果として飼い主のリラックスにもなる」。
大切にするのは"犬の幸福=人の幸福"という視点。「犬の健康や快適さを考えることは、人間の生き方を見直すことでもある。犬って正直で、瞬間を生きてる。人間はどうしても過去や未来を考えてしまうけれど、犬と暮らすと"今"に戻されます」。
その哲学は、ホテル全体に流れる"時間の設計"にも現れている。チェックインは16時、チェックアウトは11時。一般的な宿よりもゆとりを持たせている。「滞在中に"何かをしなきゃ"と思わなくていい。本を読んで、寝て、犬と散歩して、それでいい」。
軽井沢の小径には、犬の足跡が点々と続く。それを辿るように歩けば、木々のざわめきと川の水音。犬が水面をのぞき込み、しばらくして静かに尻尾を振る。その一連の動きが、まるでひとつの詩のよう。
「ウェルビーイングって、言葉にすると難しく聞こえますが、結局は"心地よく生きること"だと思っています。犬にとっても、人にとっても」。神谷さんはそう言いながら、窓の外の景色を見つめていた。
「僕はホテルを通して、"滞在"から"暮らし"への橋を架けたいんです。旅先での一泊が、人生の延長になるように。犬と一緒にいる時間が、ただの"癒し"ではなく、生き方そのものになっていくように」。
その言葉は軽井沢の空気そのもの。都会の喧騒から離れ、静かな森の中で呼吸する。犬がそっと寄り添い、人が微笑む。そこには、特別な演出もなく、ただ"あるがままの幸福"があった。

1階、2ルーム構成「デラックスカルテット」。合計セミダブルベッドが4台。ファミリー、友人など多様な利用形態に最適

もう一つのベッドルーム。写真手前にはロングソファが置かれている。犬が横たわっていいように素材を選定。この配慮がうれしい。
第Ⅳ章 軽井沢という舞台──文化としてのドッグツーリズム

正午に近づく陽光がホテルの外壁を銀色に照らしていた。森の木々と影がコントラストを高め、秋雲がゆっくりと移動していく。その穏やかな時間の中で、神谷さんの言葉が静かに響く。
「軽井沢って、特別なようでいて、実はすごく"素朴"な場所。昔から人が自然と共に生きてきた。だから、犬がここにいることも、“自然”だと思っています」。
この土地には、時間をかけて育まれた「共生の文化」がある。避暑地としての華やかさの裏に、自然と人、そして動物が共に呼吸してきた記憶が流れている。その延長線上に、ホテルの存在を置いている。
「ドッグツーリズムって、観光の"ジャンル"ではなくて、"姿勢"だと思うんです。犬を連れて旅をすることは、人が自然や社会と関わり直すこと。それを軽井沢で形にしたい」。
「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」は、"犬のための宿"ではない。犬を通して、人の感性をひらく宿だ。宿泊者が犬と過ごす静かな時間の中で、自分の呼吸や感情、思考のリズムを取り戻していく。それはまさに、軽井沢という土地がもつ"癒しの文法"そのものである。
「このホテルの理想は、犬がいることを"特別扱い"しないこと。犬がいる空間が普通で、そこにアートがあり、自然がある。その調和が、軽井沢の新しい文化になればと思っています」。
神谷さんは、これまで数多くの犬と暮らしてきた。別荘地での生活の中で、彼らは単なる家族以上の存在になったという。「犬はいつも真っすぐに見てくる。嘘がつけない。だから犬といると、自分の心の状態がすぐわかるんです」。そう言って、少し笑った。
ホテルの開業から年月が経ち、今ではリピーターも多い。季節ごとにやってくる客たちは、変わらない森の景色と、少しずつ変化する空気を楽しんでいる。「同じように見えて、実は一日として同じ日はない。それが軽井沢の魅力であり、犬と過ごす時間の尊さでもあるんです」。
このホテルには、"暮らしの深さ"がある。犬と人が共に過ごす時間の中に、アートがあり、空間があり、思想がある。それらが静かに溶け合い、軽井沢という土地の文化をゆっくりと更新していく。
──犬と人の幸福は、同じ方向を見ている。

南軽井沢交差点からほど近い碓氷バイパス沿いに建つ「ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA」。シンボリックなサインボードが目標。車利用で碓氷軽井沢I.C.より約15分

当施設ではトリミングサービス、出張トリミングにも対応(有料・要予約)。アイコニックなデザインにほほ笑む
ART HOTEL DOGLEG KARUIZAWA
住所:長野県軽井沢町長倉7-71
電話:0267-48-1191
チェックイン:16:00
チェックアウト:11:00
休業・定休日:季節により変更あり。*要HP確認
HP:https://dogleg-karuizawa.com/
*全てのゲストが快適に滞在できるよう、予約時にはHP内「ワンちゃんのご宿泊について」を確認願います。
https://dogleg-karuizawa.com/with-dog/
犬と共にあるレストラン──文化としての「共生」──『Restaurant Hamy's軽井沢』
.webp?width=800&height=533&name=18(2top).webp)
秋が深まる軽井沢を訪ねたのは、犬と人が共に過ごせる場所──その"理想形"を探すためだった。昼下がりの澄んだ空気の中に、ほんの少し薪の匂いが混じっている。
第Ⅰ章 はじまりの場所

静かな並木道を抜けると、そこに「Restaurant Hamy's(ハミーズ)軽井沢」の小さな看板が見えてくる。古くから別荘族に愛されてきたこの町で、オーストリア料理を掲げる一軒家レストラン。その扉を開けると、木の温もりに満ちた空間に、どこか懐かしい安らぎが漂っていた。テーブルの足元では、犬たちが穏やかに横になっている。客席からは小さな笑い声と、ナイフとフォークが触れ合う優しい音。厨房の奥からは、料理の香りとともに、静かな集中の気配が流れてくる。ここは、人と犬が同じ時間を共有する場所だ。

「開業のきっかけは、震災だったんです」と萩原シェフは静かに語る。レストランオーナーはもともとユニフォームを製造する会社を経営しており、2011年の東日本大震災で工場が被災した。「従業員の雇用を守りたい。それなら、別荘を改装して飲食店をつくろう」──そんなオーナーの想いから、このレストランは始まる。カテゴリも業態も決めないまま、ただ"人のつながり"を絶やさないために。
オーナーは昔からの友人でもあるオーストリアで暮らす日本人シェフを招いた。フレンチでもイタリアンでもない、軽井沢の風土にどこか似たオーストリア料理をこの地で──2011年の夏、「Restaurant Hamy's軽井沢」は誕生した。開業当初の厨房にオーストリアから帰国したシェフが立った。ヨーロッパを巡り、現地で和食店を営んでいた経験を持つ。その土地の伝統料理を理解した上で、軽井沢の食材に向き合ったという。
萩原シェフが厨房に入ったのは、3年後のこと。「当時、僕はフレンチやイタリアンの世界にいたので、オーストリア料理のことはほとんど知りませんでした」と笑う。先任シェフのもとで基本を学び、シュニッツェルやグーラッシュといったクラシックな郷土料理が、少しずつ彼の手に馴染んでいく。「フレンチは時代に合わせてどんどん進化していく料理。でもオーストリアはその逆で、古い伝統をいかに守るかという料理です」。彼はその違いに惹かれたという。軽井沢という町の静けさ、季節の移ろい、そして何より"変わらない美しさ"がそこにあったからだ。
フレンチで培った技法を織り交ぜながら、クラシックなオーストリアの骨格を保つ──それが「ハミーズのスタイル」として、少しずつ形を成していった。やがて店の空間づくりも、料理と同じく"守りながら進化する"方向へと向かう。「サードプレイスのような場所にしたい」と萩原シェフは言う。別荘の人々が、家のようにくつろぎながら、本格的な料理を楽しめる場所。過剰な装飾を演出することよりも、家庭のような温かさと余白を残したい。そしてこの空間には、いつも犬たちが寄り添っている。「うちはワンちゃんも家族の一員ですから」。オーナーとシェフの共通した思いが、この店を特別な場所にしている。
第Ⅱ章 人と犬とが同じ食卓を囲む幸福

ドッグメニュー:「ごほうびステーキ」安全が担保されたオーストリア産牛肉を使用。“ご褒美”の名称はその豪華さから、スタッフが考案した。食花で囲んで色彩にもこだわる。テーブルには犬種にあわせ食べやすいようにカットしてサーブする ⒸRestaurant Hamy's軽井沢
.webp?width=800&height=534&name=22Hamys_(250205_0201%202).webp)
ドッグメニュー:「トマト煮込みハンバーグ」牛と豚の合挽肉に豆腐、卵、牛乳、パン粉を混ぜ、そしてトマトソースで煮込んだ栄養価の高い逸品 ⒸRestaurant Hamy's軽井沢
.webp?width=800&height=534&name=23Hamys_(250205_0175).webp)
ドッグメニュー:「鶏胸肉とほうれんそうのミートローフ」鶏ムネ肉を細かく刻み、卵とホウレン草とともに優しく焼き上げる。塩分は使用していない。鶏肉ならではの味の深みが楽しめる ⒸRestaurant Hamy's軽井沢
.webp?width=800&height=534&name=24Hamys_(250205_0179).webp)
ドッグメニュー:「お米とビーンズ、チキンのミートローフ」鶏ムネ肉と白米の炊き込みと、カボチャのピューレに3種類のビーンズと卵をミックス2層になるよう蒸した食感も意識している ⒸRestaurant Hamy's軽井沢
.webp?width=800&height=534&name=25Hamys_(250205_0185).webp)
ドッグメニュー:「信州サーモンお豆のテリーヌ」長野県佐久穂町産信州サーモンに豆腐と卵を混ぜミンチ状に。そしてゆっくり丁寧に焼き、素材の味を感じられるように配慮した ⒸRestaurant Hamy's軽井沢

“人間用”のメニューと同じくデザインされたドッグメニュー表。オンラインストアでもさまざまなフードを販売している
「Restaurant Hamy's軽井沢」が他のレストランと異なるのは、犬と人が同じ空間で同じ時間を共有できるという点にある。それは単なる「ペット同伴OK」ではなく、"家族としての犬"を前提にした思想から生まれている。萩原シェフは言う。「犬を入れるかどうかという前提ではなく、オーナーが保護犬活動を長くやっていて、"犬も家族だから、一緒に食事するのが当たり前"という考えです」。店が犬を迎え入れたのは、商業的な判断ではなかった。もともとはテラス席だけが犬同伴可能だったが、「それだけでは本当の共生にはならない」との想いから、現在では室内のメインダイニング、複数の個室にも犬たちの姿がある。
その背景には、オーナーが見てきたヨーロッパの"犬文化"がある。オーストリアやドイツを訪れ、犬が電車に乗り、カフェやレストランで当たり前に過ごす光景を目の当たりにした。そこには、犬を単なる愛玩動物としてではなく、社会の一員として受け入れる文化的な基盤があった。ドイツ語圏では、飼い主に対する教育と行政の連携が徹底している。マナー講習に参加しなければ、地域コミュニティに加われない。犬が公共の場で吠え続ければ通報され、職員が飼育状況を確認する。その厳しさは、"共生のためのルール"として根付いている。「シェフ、これなのよ」──オーナーがそう語ったとき、萩原シェフはその意味をすぐに理解した。「日本では犬文化はまだ発展途上。でも、軽井沢から少しずつ変わっていけたら」と語る。
もちろん、課題もある。犬が苦手な人もいるし、吠え声やトラブルのリスクもある。しかし、同店の設計は偶然にもそれを受け入れる形になっていた。広めの間取りと個室構造が、互いの距離を柔らかく保ってくれる。「苦手な方がいれば、個室を分けて対応する。でも"犬がいるからダメ"という線引きはしない」。それが、この店のポリシーだ。萩原シェフは微笑みながら続ける。「うちのお客様はマナーがいいんです。犬同士が吠え騒ぐことは年に数回あるかどうか。お店の空気を感じて、自然と落ち着くのかもしれません」。
印象的なのは、犬をめぐるエピソードだ。若い夫婦が"愛犬と一緒に結婚式をしたい"と願い、レストランウェディングを開いた。「他では断られたけど、ここならできる」と。新郎新婦の隣で、大切な家族である犬が穏やかに座っている。それは祝福の輪の中に、ごく自然に存在していた。「そういう時、この店をやっていてよかったと思います」と萩原シェフは目を細めた。
犬の存在は、料理の世界にも静かに変化をもたらした。メニューには「ドッグメニュー」が並ぶ。テリーヌ、ハンバーグ、サーモン──どれも人間と同じクオリティで作られている。「どうせ作るなら、本物の料理人が考えた犬のごはんを」。それは料理人としての誇りの表れでもある。犬のごはんには、塩もソースも使わない。食材の持つ甘みや香りだけで構成する。「見た目も美しくしてあげたい。飼い主さんが"綺麗だな"と思う料理は、犬にも伝わると思っています」。
実際、その「ごほうびステーキ」やテリーヌは人気を集め、オンラインでの販売も始まったという。中には「食欲の落ちた老犬が、ハミーズのごはんだけは食べる」と定期的に注文してくる飼い主もいる。「きっと、ちゃんと作れば思いは伝わるのだと思いますね」と、萩原シェフは少し照れくさそうに笑う。
穏やかな空気の中で、犬も人も同じように時間を過ごし、互いを尊重し合う光景が日常になっている。「犬がいるから、やらない」ではなく、「犬がいるからこそ、できることがある」。その発想が、この食空間を唯一無二にしている。
第Ⅲ章 オーストリアの風と、軽井沢の記憶

軽井沢高野菜と周辺生産農家から仕入れたレタス、ビーツ、根菜と食花を用いたサラダ。レモンとタマネギの自家製ドレッシングがけ。オリジナルレモンドレッシングはオンラインストアで購入可能

“看板メニュー”のウインナーシュニッツェル。オーストリア・ウイーンの名物料理。仔牛肉を厚さ2〜3mmになるよう薄く叩く。この厚さは萩原シェフがたどり着いた最適解。ナイフでの切れ、噛みごたえのバランスが絶妙。衣は包むというより“纏う”繊細さがある

ハミーズ・ハンブルグステーキ。国産牛と背脂、卵とタマネギでつくられたハンバーグ。かなりの粗挽きにより食べごたえと上質な肉が持つ深い味わいに驚く。さらに上に添えられたアボカドと半熟卵の調味は素材が互いを引き立てる。

オーストリアを代表するチョコレートケーキ=ザッハトルテ。中心層にあんずジャムを挟みオーガニック100%ビターチョコレートでコーティング。こだわりはそのソフトさ。ゆえにクリームとの絡みがバランス良くまとまる。パティシエの修行を経た萩原シェフならではの繊細さ

オーストリア、ドイツの伝統的家庭料理=アップフェルシュトゥルーデル。透けるほど薄い生地にリンゴとレーズンを包み込んだデザート。個性的なアップルパイとアイスクリームがつくり出す酸味と甘味が楽しい“甘い誘惑”
厨房に立つ萩原シェフの動きは、静かだが迷いがない。手元にあるのは、長野の畑で採れたレタスやビーツ、根菜たち。それらがプレートの上で軽やかに組み合わさり、オーストリアのクラシックな料理と溶け合っていく。「食材ありき、環境ありきなんです」とシェフは言う。
数年前、萩原シェフはオーナーの勧めでオーストリアへ渡る。現地では、湖畔の農家やチーズ職人を訪ね、野菜やミルクを生み出す人々と直接言葉を交わした。そこには、食材を「命」として受け取り、感謝と敬意をもって調理に向き合う文化が息づいていた。「牛を飼う人たちは、毎日"ありがとう"って声をかけていました。その姿を見て、ああ、料理ってこういうことなんだなって感じました」。目に映ったのは、"進化"ではなく"循環"だった。自然の恵みを頂き、次の季節へとつなぐ。その思想が、全ての料理に静かに流れ込んでいる。
たとえば、前菜のサラダ。軽井沢周辺の農園や、元・種苗農家の男性が育てる小さな畑──から届く野菜を使っている。「地元の方が自分で種を選び、愛情を込めて育てています。それを仕入れて、お皿の上にそのまま乗せるだけで、もう十分に美味しい」。ドレッシングは、創業当時からのレシピをアレンジしたもの。玉ねぎとレモン、黒胡椒のシンプルな構成に、オーナーの想いを受け継ぐ味がある。
“看板メニュー”のシュニッツェルは、伝統と実験のあいだに立つ一皿だ。叩いて薄く伸ばした仔牛のロース肉は、サクッとした衣の下に、やわらかく、ほのかに甘い香りを残す。「本場ではモモ肉を使うけど、日本では手に入りにくいんです。だから、うちは乳飲み子のロースを使います。臭みがなくて、繊細な味になる」。絶妙な食感を誘う2〜3ミリの厚みに叩く、その感覚は長年の勘から生まれる。
そして、もうひとつの看板メニュー、ハミーズ・ハンブルグステーキ。和牛と交雑牛を合わせ、背脂を練り込む。つなぎは卵だけ。「塩と胡椒と卵、それだけでいい。余計なものを入れない方が、肉の声が聞こえるんです」。焼き色をつけて、蒸しながら休ませる──そうして生まれるピンク色の断面は、レアでもミディアムでもない、このキッチンだけの焼き加減。ソースはりんごと醤油、玉ネギ、そして少量のフォンドボー。和の香りとフレンチの技法が溶け合うその味わいは、"味覚の国籍を限定しない温もり"を感じさせる。
デザートのザッハトルテもまた、"正統"と"軽井沢流"の間で生きている。本場より軽やかに、甘さを抑え、有機チョコレート〈カオカ〉の68%カカオを使う。「72%だと苦いし、60%台前半だと甘い。68って、ちょうどいいバランスが取れた大人の味です」。その数字に、萩原の感覚的な美学が滲む。
どれも少し控えめで、けれど一皿ごとに誠実な重みがある。それはきっと、オーストリアの牧草地で感じた"命への敬意"が、軽井沢の森で静かに息づいているからだろう。
第Ⅳ章 ドッグリゾートの聖地、軽井沢のこれから

テラス席での食後、飼い主の足元で満ち足りた時間を共有する愛犬。思い出の1ページを編む

ふと見上げると秋の深まりが。犬たちも同じ景色を見ているのだろうか
取材の最後、店の奥から新聞社取材対応のため来店していたオーナーが顔をのぞかせた。上質な生地が奏でるシルエットが美しい黒のスーツ。年齢を重ねた優しさと、凛とした意思を湛えた人だった。経営を支え、そして「犬と共に生きる文化」を軽井沢に根づかせてきた人物である。
「利益追求では、とてもやっていけませんよ」と彼女は笑う。冬の軽井沢は閑散期に入る。雪に包まれる季節。それでも店を閉じないのは、「ここに帰ってくる人たちがいる」からだという。オーナーはゆっくりと言葉を紡ぐ。「15年前に店を始めた頃は、私たちの世代──別荘を持っていた上の世代の方々が中心でした。でも、今はその息子さんや娘さんたちがいらっしゃるようになりました。世代が変わっても"軽井沢らしさ"を理解している人たち。私たちの使命は、それを次の時代にきちんと手渡すことなんです」。
「犬のいない生活は、もう考えられませんね」。彼女は静かに続ける。「夫と一緒に保護活動を始めて、ずっと犬たちと暮らしてきました。夫が病に倒れたとき、最後に口にしたのは亡くなった愛犬の名前でした。きっと迎えに来たんだと思います」。言葉に涙はなかった。けれどその声には、深い愛情と敬意が宿っている。「犬の保護やレスキューは、仕事でもなく、生活のためでもない。でも、趣味という言葉も少し違うんです。命を守るということは、自分が生きている証でもある。それが、私の"生き方"なんです」。
その言葉を聞いたとき、「軽井沢ドッグツーリズム」という言葉の意味を改めて考えさせられた。それは単なる観光や経済活動ではなく、人と犬が互いを尊重しながら生きる"文化"をつくることに他ならない。
テラスでは、昼下がりの陽射しの中で、犬たちがゆっくりと眠っていた。純白のカップに小さく立ち上るコーヒーの香り。木漏れ日の奥で、シェフの笑い声が微かに聞こえる。この町の時間は、急がず、穏やかに流れている。オーストリアの伝統と軽井沢の空気が混ざり合い、人と犬とが同じ食卓を囲む──その光景こそが、『Restaurant Hamy's軽井沢』という場所の"物語"なのだと思う。
軽井沢の未来は、きっとこんなふうに続いていく。木々のざわめきと犬たちの足音、そして食を生む人たちの音が、静かに重なり合いながら。

建物壁面の店舗アイコン。そこに犬の姿が描かれている。「Restaurant Hamy's軽井沢」の理念の象徴

ランチ営業を終え、アイドルタイムのひととき。萩原シェフと談笑するスタッフ。皆が愛犬家だ。当店のホスピタリティはこうして生まれてゆく

メインダイニングの一角。余裕ある空間づくりと配置がゲストの快適さを約束する

2部屋ある個室のひとつ、10人が利用可能な空間。もちろん犬の同伴OK

右壁面に掛けられたアート。軽井沢町を拠点に活動するアメリカ人アーティスト=デビット・スタンリー・ヒューエット氏の作品。「武士道」をテーマとした作品群の一つだ
Restaurant Hamy's
住所:長野県軽井沢町軽井沢1263-5
電話:050-1725-1779
営業時間:11:00〜14:00(ランチタイムLO)
17:00〜20:00(ディナータイムLO)
休業・定休日:季節により変更あり。要HP確認
HP:https://hamys.jp/information/schedule/
備考:年末年始休業12/30〜1/2(予定)
Go NAGANO編集部(佐藤)
閲覧に基づくおすすめ記事