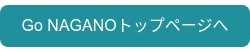特集・紅葉ハイキング&自然を味わう Vol.2 軽井沢『MANO』オーナーシェフ・西本竜一さんに学ぶ、焚き火を使ったアウトドア料理、地元野菜やキノコの楽しみ方
薪火料理の第一人者・西本竜一シェフが手がける体験型レストラン「MANO」を訪ね、薪火で引き出す食材の魅力と、たき火調理の奥深さに迫ります。さらに、シェフが注目する旬の食材と、その味覚をより深く楽しめる周辺のキャンプスポットもあわせて紹介。紅葉が美しい季節、自然と火と食が織りなす“秋のごちそう時間”へご案内します。

薪火から生まれる信州ガストロミー「MANO」の世界観
薪火料理「MANO」。西本竜一シェフの世界観を凝縮したカウンター8席の空間で、薪火を駆使した料理を供する、五感で味わう体験型レストランだ。
この店を手がける西本シェフは、22歳でスペインへ渡り、本場で料理を学んだのち帰国。2024年7月、観光客で賑わう中心街から少し離れた、自然豊かで静かな南軽井沢に「MANO」を開業した。
こちらで味わえるのは、自然と火が織りなす五感で楽しむ薪火料理の世界。シェフ自ら山に入り、きのこや山菜などの季節の恵みを採取。焚き火を用いて丁寧に調理し、自然の滋味をそのまま味わえる一皿へと仕上げている。
西本シェフが薪火の魅力に目覚めたのは、幼少期のこと。家族でキャンプに出かけた際、たき火を囲んで食材を焼いた体験が原点だという。自然の中で火を起こし、その場で食材を焼いて味わったとき、「火が食材をこんなにも変えるのか!」と驚き、その感動が今の料理づくりの根幹にも息づいている。
2つめの出会いは、本格的な薪火料理を学ぶために渡ったスペインで。
「『エチェバリ』という店で、薪火と料理の融合を目の当たりにしたんです。修業したのは別の店だったんですが、ここでの体験が自分の進む道を決定づけました」
スペイン・バスク地方にある「エチェバリ」は、薪火料理の名店として知られ、世界の料理家が訪れることでも知られている。バスク地方は、古くから「アサドール」と呼ばれる炭火や薪火を使った食文化が根付き、肉や魚をシンプルに焼き上げる技術が受け継がれてきたエリアだ。なかでも、名店「エチェバリ」のシェフは“薪火の魔術師”と称される存在。西本シェフがその料理哲学に強く影響を受けたというのもうなずける。

薪火料理は、ただ炎に食材をかざせばよいというものではない。
薪の組み方や熾火(おきび)の状態を見極め、炎の力とじんわりとした余熱を使いわけることが重要なのだと西本シェフ。
「煙や熱の流れ…上昇気流を読むことが大切です。風の強さや時間帯によっても火の表情は変わってくるので。環境を感じ取りながら、どの位置に食材を置くかを考えるんです」
使用している薪は主にカラマツやナラ材など。扱いやすいのはナラ材だが、あえて扱いが難しいとされるカラマツも使用する。「浅間山麓でたくさん採れるんです。用途が少ない森林資源を活用するのも、私の活動目的の一つでもあるので」
炭では得られない、薪ならではの香りを食材にまとわせることも薪火料理の大きな魅力だ。
「例えばウィスキーなどの樽熟成に使われるカシの木はバニラのような香りを持っています。元々木が持つバニリンという成分が発生し、強く濃かったお酒が甘さを感じて飲みやすくなる。でも糖になったわけではないので実際に甘いわけではない。僕の薪火料理も同様で、薪火からバニリンを発生させ、香りを食材にまとわせているんです。それが僕の薪火料理の特徴です」
味覚、食感に加え、香りのレイヤーを重ねていくことで、西本シェフでしか作り出せない一皿へと昇華させる。「MANO」が唯一無二と評されるのは、薪火を繊細に操り、香りの余韻までを引き出す一皿を生み出しているからであろう。


ここまでの話を聞くと、一般の人が焚き火料理をおいしく仕上げるのは、かなり難易度が高いように感じる。
キャンプでの調理は、味よりも雰囲気重視。焼肉のタレをかけてしまえば、何でもそれなりにおいしく感じてしまうものだが、せっかくの地元素材をそんなふうに扱ってしまうのは、やはりもったいない。
そこで今回は、焚き火料理のプロ・西本シェフに、誰でも焚き火料理を楽しむためのアドバイスを伺った。
「いきなりお肉を焼くのは難しいので…」とシェフが出してきた食材は“パン”。肉はしっかり火を入れなければ食べられないが、入れすぎれば硬くなる。だからこそ、火加減を学ぶにはパンから始めるのがよいという。
「パンは糖分や油分が多く焦げやすい。そこから鶏肉、そして牛肉へと段階を踏むことで、火の扱い方を徐々に理解していくことができるんです」
酸化して炭化してしまうと風味が損なわれるため、香ばしさのピークで火入れを止める技術が重要になる。まずはその加減を習得することが、焚き火調理の第一歩だ。本番のキャンプは屋外なので、より環境のハードルも高くなる。焼き方の基礎が身に付いていれば、調理自体を楽しむことができ、仕上がりもぐっとおいしくなるはずだ。


次にシェフが焼いてくれたのは、狩猟後すぐに丁寧な処理が施された新鮮な鹿肉。脂が少なく乾きやすいため、一般の食卓で調理するのは難しいといわれる食材である。
「表面にオイルを塗って水分を逃さないようにします。僕はオイルや水、お酢をブレンドしたスプレーを使います。素材によって使い分けることで、肉がパサつかず旨味を引き出せる。今日はオイルを使います」
鉄板に油をひくのではなく、食材に塗るのが焦げ防止に効果的なのだという。
「表面のタンパク質を凝固させた方がいいので、置きっぱなしにしないで、マメにひっくり返していく。表面を焼き固めるというイメージです。こうすることで肉汁が閉じ込められ、柔らかい肉質に仕上がります」
また、野菜においても、焚き火調理では素材ごとの性質を見極めることが重要だ。糖分を多く含む野菜は焦げやすいが、そのギリギリの火入れを生かすことで、香ばしさと甘みがより際立つのだという。
「ズッキーニやトウモロコシは、焦げ寸前まで焼くことで甘みと香ばしさが引き立ちます。逆に、茹でたり蒸したほうが美味しい野菜は、無理に焦がしても旨味が出にくい。野菜の個性を知ることで、たき火料理はもっと楽しくなりますよ」

秋が深まるにつれ、アウトドア料理の食材として注目されるのが“キノコ”。
西本シェフがキノコの世界にのめり込んでいったきっかけは、白馬村のスノーピークで働いていた頃。“きのこ博士”との出会いからだった。
「師匠は当時で80代。ほぼ引退されていたんですが、僕を弟子にしてくれて、一緒に山に入らせてもらっていたんです」
子どもの頃から自然に親しみ、キノコにも興味を持っていたので、図鑑などから独学で知識を身につけていたという。「もともと持っていた知識や興味が、師匠との出会いと経験を通して、より確かなものになっていきました」
師匠の元で4年間、キノコへの造詣を深めた西本シェフ。
「そこで師匠から『君はキノコの判別もできるし、そろそろ自分のお店を出したらどうだ?』と言われ、独立を決意したんです」

MANOをオープンしてからも、ほぼ毎朝山に入り、自らキノコを採る日々なのだという。長野県だけでなく、群馬県の山にも足を運び、新しい山を紹介してもらいながら、少しずつ採取ポイントを広げてきた。
「一番好きなのは香茸(コウタケ)です。収穫量は多くないけど、香りが抜群で旨味もしっかりしているキノコです」。コウタケはマツタケ以上の風味と香りを持つといわれるキノコで市場には出回ることも少なく“幻のキノコ”と呼ばれている。
こうして山中で採取された天然キノコは、薪火で丁寧に火入れされ、「秋のスペシャリテコース」の一品として供される。ほかにも、香りを生かしたソースや付け合わせなどにも姿を変え、それぞれの個性を際立たせながら、料理に奥行きを与えてくれる。素材の持ち味を余すことなく引き出すのは、自然と向き合い、食材の声に耳を傾ける西本シェフの姿勢そのものだ。
そんな一皿に出会えるからこそ、人はMANOへと足を運ぶのだろう。


【MANO】
住所:長野県北佐久郡軽井沢町発地553-3
問い合わせ:Instagramのプロフィール欄より
営業時間:ランチ12時~15時、ディナー18時~21時(ランチは土・日曜のみ)
定休日:火・水曜
HP:https://www.instagram.com/mano_karuizawa/
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/QutaPUF9dSXNeYHH9
西本シェフが注目する、秋を感じる信州食材とアウトドアフィールド
秋の気配が深まる信州の山々。きのこをはじめ、山の恵みが旬を迎えるこの季節は、焚き火の香りが料理の魅力をいっそう引き立ててくれる。自然と向き合い、食材の声に耳を傾ける料理人・西本シェフが注目する、信州の秋の味覚と、その産地周辺にあるキャンプ場3選をご紹介。西本シェフの視点をヒントに、食と自然を味わう秋キャンプへ出かけてみよう。
廻り目平キャンプ場 ふれあいの森@川上村

奇岩群に囲まれた金峰渓谷の中にある廻り目平観光施設は、キャンプ場のほか、フリークライミングの聖地としても知られ、日本のヨセミテとも呼ばれている。施設内には、金峰山荘宿泊者は無料で利用できる大浴場を備える「金峰山荘」や、フリーサイトで、好きなスペースにテントを張れる「廻り目平キャンプ場」、少し離れた場所に位置する「ふれあいの森」がある。
廻り目平キャンプ場は、コインシャワーや水洗トイレ、炊事場などの設備があり、直火で焚き火ができるなど、大自然でのアウトドアライフを満喫できる。一方「ふれあいの森」には、車で入れるキャンプサイトと6棟のキャビン、1棟のバーベキューハウスがあり、隣には金峰山川が流れ、川のせせらぎを聞きながらのキャンプが楽しめる。

〈西本シェフコメント〉
「レタスの生産地としても知られる川上村。キャンプ場へ行く道のりに、地元野菜を販売する『森の駅 マルシェかわかみ』があるので、そこで野菜などを購入してから向かうといいですね。そろそろ天然キノコも豊富に並ぶ時期。また、高原の冷涼な気候で育ったトマトも、秋には甘みが増しておすすめです」
【廻り目平キャンプ場 ふれあいの森】
住所:南佐久郡川上村大字川端下546-2
問い合わせ:0267-99-2428
営業時間:利用受付時間【廻り目平キャンプ場】7時~20時、【ふれあいの森】8時~20時 ※金峰山荘にて
定休日:11月中旬~4月中旬
料金:【廻り目キャンプ場】1人/1泊900円、【ふれあいの森】1人/1泊700円、オートキャンプ1サイト/1泊3,500円※テント1張り、自動車1台
HP:http://w2.avis.ne.jp/~mawarime/
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/F95mszAdFoPBzRs9A
高ソメキャンプ場@松本市

100区画、自然の地形を生かして配置されているため広さや形が異なり、車の横付けも可能で荷物の移動もスムーズ。場内は6つのエリアに分かれ、家族連れに安心のエリアからソロで静かに過ごせるエリア、電源付きの快適なエリアまでそろい、利用者のスタイルに合わせて選ぶことができる。
また、場内には釣り池があり、イワナやニジマスの釣り体験も可能。レンタル竿も用意され、初心者や子どもでも気軽に楽しめる。さらに、春の山菜採りや夏のホタル観賞、昆虫採集、秋の紅葉散策やキノコ採り、コーヒーを片手に早朝の乗鞍岳を眺める静かな時間など、四季折々の自然を身近に感じられる体験も訪れる楽しみのひとつ。

〈西本シェフコメント〉
「松本市奈川は天然キノコの産地として知られているエリアです。キノコ狩りをガイドしてくれるツアープランもあるそうなので、利用してみたらキノコの知識が深められていいかもしれませんね」
※ツアーに関してはこちらを参照 https://daiji-outdoor.com/
【高ソメキャンプ場】
住所:松本市奈川2212-16
問い合わせ:0263-79-2919
営業時間:9時~17時
定休日:水曜、冬季期間
料金:テントサイト・オートキャンプ:【区画サイト料】1人/1泊500円、2名以上/1泊1,000円 【宿泊料】大人(中学生以上)/1泊1,600円~、子ども(小学生)/1泊800円~、幼児無料
HP:https://takasome.furusatonagawa.com/
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/amJiXo1MCiij6XRR9
スノーピークランドステーション白馬

スノーピークランドステーション白馬は、白馬駅から徒歩圏内の市街地に佇む体験型複合施設。屋内施設には、アウトドアギアやアパレルを販売するスノーピーク直営店やレストラン、カフェ、観光案内所を併設。さらに林間サイト内には世界的建築家・隈研吾氏とスノーピークが共同開発したモバイルハウス「住箱-JYUBAKO-」2棟、快適に過ごせるよう、ベッドに加えエアコンと冷蔵庫も備えた設営済みテントサイト1サイト、持ち込みで宿泊できる林間サイト7サイト、芝生サイト2サイトの9サイトを設けている。店舗併設で安心なうえ、林間サイトにはAC電源付きのサイトもあるなど、キャンプデビューにもぴったり。宿泊プランには、隣接する温泉施設の入浴券が付き、夜は温泉に入って設営時の汗を流すもよし、澄んだ空気の中で焚火を囲んだり、星空を眺めるのもおすすめ。

〈西本シェフコメント〉
「スノーピークのギアがレンタルできるのも魅力の一つ。購入前に実際に使ってみられるのはうれしいポイントです。近隣には地元野菜やオリジナル商品が充実したスーパーもあり、キャンプ前の買い出しにも便利です。秋には白ナスや食用ほおづきなど、白馬ならではの野菜が並ぶこともあるので、ぜひ探してみてください」
【スノーピークランドステーション白馬】
住所:北安曇郡白馬村大字北城5497
問い合わせ:0261-75-1158
営業時間:11時~19時
定休日:なし
料金:キャンプサイト1泊2名9,570円~
HP:https://www.snowpeak.co.jp/landstation/hakuba/
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/PceAvGbHEn2eGcM6A
撮影:宮崎純一 取材・文:大塚真貴子、児玉さつき
閲覧に基づくおすすめ記事