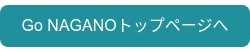地産地消を貫くオーベルジュの歩み
紅葉が見頃を迎えた秋の蓼科高原。
「オーベルジュ・エスポワール」のオーナーシェフとして、30年近くフランス料理を手掛けてきたのが藤木徳彦シェフだ。
1998年に東京から家族で蓼科へ移住。両親は当初、アットホームなペンションの開業をイメージしていたが、オーベルジュを提案したのは藤木シェフだった。
「フランスを訪れたときに出会ったオーベルジュに強く惹かれていたんです。タクシーで行かないとたどり着けないような田舎のはずれにあるのに、いつも満席状態。どんな料理を出しているんだろうと思ったら、徹底した地産地消。地元の季節素材を使ったしっかりした料理を提供するのに、接客はあたたかい家族のおもてなし。日本でこんな店をやりたいなとずっと思い描いていたんです」

そして1998年4月に「オーベルジュ・エスポワール」がオープン。
「地元のものを使いたいと思っていたんですが、今でこそスーパーや道の駅などで地場産の野菜を気軽に買えるようになったけど、当時はそんなこともなく。八百屋の店主にどうしてかと聞いたら『藤木さん、流通を知らないの?長野県は生産県だけど、全部首都圏へ出荷されていくので、我々にも県内産を仕入れるルートはないんだよ』と言われてしまったんです」
県内産の素材を入手する手段がなかったので、やむなくフランスやイタリア、築地で仕入れた食材を使い料理を提供。
「それがゴールデンウイークのことでした。そしたらお客様から『銀座でも食べられる料理をなんでわざわざ蓼科まで来て食べないといけないんだ』とお叱りをうけたんです。それはごもっともだなと。それでどうしたら地元産を入手できるかを考え行動しました」
藤木シェフに気づきを与えてくれたその人物は、今でも店に通い続けてくれているのだという。
生産者から直接食材を仕入れるため、自ら足を運んでみたが「飛び込みで行っても、すぐに売ってもらえるわけではありませんでした。何度も通い、徐々に信頼関係を築いていったんです」
そうした地道な努力が実を結び、やがて人づてに生産者を紹介してもらえるようになり、つながりは少しずつ広がっていった。
山の恵みが導いた、ジビエとの出会い
生産者とのつながりを深める中で、キノコ鑑定士との出会いにも恵まれた。共に山へ入り、天然キノコの種類や特徴を教えてもらったのだという。
「わざわざヨーロッパから輸入しているキノコが、実は身近な山にたくさんあったんです。キノコの魅力をその方から本当にたくさん教えていただきました」と藤木シェフ。
そしてキノコの時期が終わり、冬を迎えようとしていた頃のこと。
「野菜もないしキノコも終わり、このへんじゃ寒天しかないような状況で、さて困ったなと思っていたら、農家を営む母娘が食事に来てくれたんです。『シェフ、私たちも困っているのよ』と言うので話を聞いてみると、おじいちゃんが狩猟で鹿を獲ってくるものの、鹿肉料理が家族には不評だと。それで、冷凍してあった鹿肉を試しに分けてもらって食べてみたら、これがすごくおいしかった。“ああ、信州にはジビエがあるじゃないか”と気づいて、店でも提供することにしたんです」
冬の食材としてジビエを使わざるを得なかったこと。そして、信州のジビエがとてもおいしかったこと。それが、ジビエと関わるきっかけだった。

「ジビエは農家さんのルートと同じ。流通がないので直接取引するしかない。なので、直接猟師さんのもとへ出向いて、まずは人間関係を築くことからはじめました」
藤木シェフ自身が猟をすることはないが、狩猟の現場に同行したことは何度もあるという。
「そうした世界を実際に見ることができ、猟師さんたちと出会えたことは、自分にとって大きな財産になりましたね」
20年以上前は、イノシシや鹿もそれほど多く獲れるわけではなく、ジビエは貴重な存在だったという。
「当時は今より頭数も少なく、人のいる場所に姿を見せることもほとんどなかったんです」
そんな中で出会った一頭一頭の命を、無駄にせず、人が生きていく糧として皆でいただく――。
「猟師と料理人、“命を生かそう”という思いは一緒なのだと実感しました」

狩猟の現場でハンターと直接言葉を交わす藤木シェフ。山の恵みを料理で生かし命をつなぐ ©オーベルジュ・エスポワール

冬の猟に立ち会い、食材の背景を肌で感じた ©オーベルジュ・エスポワール
藤木シェフの行動力が、信州ジビエの未来を切り拓く
“信州ジビエ”の評判が広がるにつれ、冬の閑散期にも多くの人がエスポワールを訪れるようになっていった。
そんな中、自治体の観光課から「地域の食材を生かした料理で、地域の魅力を発信したい」との相談を受け、藤木シェフがメニューづくりを担うことになったという。
「ところが、上伊那で獲れた山鳩と鹿肉をメニューに入れたところ、保健所から『待った』がかかったんです。保健所的には『ジビエを出すことは認められない、イベントを中止にするか、この2つをメニューから外すように』と言うんです。でも毛付きの鳩なんてヨーロッパから食材として我々の手元へ届くし、鹿肉だって昔から地域で食べられていて、旅館でも普通に出していたじゃないですかと。でもダメなものはダメと…」
そこで藤木シェフがとった行動が――「当時の知事。田中康夫さんがたまたまうちの店に来てくださったことがあったので、思いを綴った直訴文を送ってみたんです」
するとすぐに知事から電話があり、わずか2日後には開催の許可が下りたという。
「保健所に“なぜダメなのか”と尋ねたところ、『ジビエは国が食肉として認めていないので、そもそも食品ではないんです』と言われたんです」
当時はジビエに関する明確なルールがなく、それが保健所の許可を得るうえで大きな弊害となっていた。
こうした課題を前に、藤木シェフは再び知事への提案を試みた。当時、田中康夫元知事が掲げていた政策のひとつが、“信州ワインの普及”だった。
「知事に提案をしたんです。信州ワインにはジビエだと。フランスの美食家は狩猟期になると、こぞってワインとジビエを楽しむ、これを信州でもやりましょう。信州ワインとジビエを冬の目玉にしませんか?と」
とはいえ、ルールがないままでは、保健所の許可は下りない。
「それならルールを作りましょう、という話になって、“信州ジビエ衛生管理ガイドライン”が整備されていったんです」

鳥獣食肉利活用推進議員連盟(ジビエ議連=石破茂会長)に呼ばれ、ジビエ料理をふるまうことも多い ©日本ジビエ振興協会

日本ジビエ振興協会 代表理事として多くのシンポジウムにも出席し、講演を行っている ©日本ジビエ振興協会
信州が起点となったジビエのガイドライン。2014年には厚生労働省も「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針」を設け、衛生面での基準が全国に広がっていった。
藤木シェフの提案により調理法まで紹介した長野県の取り組みをモデルケースとし、各県のガイドラインが整えられていった。
その一方で「まだ国は、“ジビエは食肉として認めていない”というスタンスだったんですよね。そんな時にある新聞記者の方から『直接、石破幹事長(当時)と話した方がいいよ』と勧められ、お会いする機会を設けていただけたんです」
そこで藤木シェフは、鹿による農作物の食害など地方が抱える現状を訴えたという。
「石破さんに、“害獣は捨てればゴミだけど、生かせば資源になる”と伝えたんです。すると『じゃあ藤木さん、私は何をやればいい?』と聞かれたので、“国としてジビエを食肉として認めてほしい”とお願いしました」
それを聞いた石破幹事長(当時)は、その場で厚生労働省に電話をかけ、すぐに話を通してくれた。そして2014年11月、国として国産ジビエが正式に“食肉”として認められることとなった。
田中康夫知事(当時)からはじまり、石破幹事長(当時)にも直訴へと続いた藤木シェフの働きかけにより、国の制度整備を後押しする流れを生んでいった。藤木シェフがその一歩を踏み出していなければ、国産ジビエがここまで広く普及することはなかったかもしれない。

ガイドラインが整えられ、安全な国産ジビエが手に入るようになってはきたが、まだまだ課題は多いと藤木シェフ。
「食肉として位置づけられたので牛肉や豚肉と同じ扱いなのに、大手企業はジビエを扱わないんです。そのため価格が安定しない。日本ジビエ振興協会として今後取り組まないといけない課題は、ジビエの市場を作ることです」
2018年には「国産ジビエ認証制度」という、消費者に安全なジビエを届けるために食肉処理施設の衛生・品質管理を審査する制度を設けた。これも藤木シェフの経験が元となり設定されたのだという。
「たまたま仕入れた鹿肉が、明らかに屋外で処理されたものだと気づいたんです。長野県の検査機構に出したら、先方も驚くほど多くの菌が検出された。せっかくガイドラインをつくって一生懸命普及させても、食品事故が起こったら一発で厚労省はストップさせる。これではいけないと農水省に提案し、2年間仕組みづくりを行い、2018年に制度ができたんです」
国産ジビエの法制度がここまで整っているのは、すべて藤木シェフの提案と行動があってこそ――改めて、その影響力の大きさに驚かされる。
「私が本来やりたかったのはこういうことじゃないんですけどね(笑)。私が目指していたのは “おいしいジビエの普及”。でもそもそも手元に届くジビエが不衛生だと、おいしい料理も作れないということで、インフラを整備していたらこんなに時間がかかってしまったんですよね」

ジビエ普及の鍵は“おいしい”を多くの人に伝えること。
ジビエの法制度が整った今、次の課題は「いかに流通させるか」だと藤木シェフ。現在、全国で年間約120万頭の鹿やイノシシが捕獲されているが、そのうち食用として活用されているのはわずか1割。残りの9割は廃棄されているのが現状だという。
「それだけ多くが廃棄されていると聞くと、“じゃあタダで手に入るんじゃないか”と思う料理人もいる。でも、処理施設は運営していかなければならず、そのためには当然ながら費用がかかる。だから『この部位は○○円です』と提示すると、“高いね”という反応になる。結果として、食用に活用される割合が10%からなかなか増えないんです」
こうした現状を変えていくには、 “ジビエはおいしい”ということを消費者に認識してもらうことも重要だ。
「ジビエが出始めの頃は、まだ料理人の調理技術も追い付いていなかった。野菜炒めに豚肉の代わりに鹿肉を入れたメニューを出されたけど“硬くておいしくなかった”と。そう感じた人も少なくなかったんじゃないですかね」
当時ジビエを食べてマイナスイメージを抱いてしまった人の印象を払拭するために「調理技術の普及も行っています。調理師学校の授業にも、ジビエの扱い方を取り入れてもらっているんですよ」

鹿肉のスジをとる。スジや骨などはダシをとりソースに。余すことなく命をいただく

雄と雌では筋肉のつき方がまったく異なる。肉質が柔らかいのは雌鹿で、断面にもそのきめ細かさが表れている

鹿肉本来の風味を損なわないよう、下処理は天然塩のみを使用
信州の森と向き合うガストロノミー。藤木シェフの一皿
信州ジビエ素材を、料理人としてどう生かしているのか、エスポワールのシェフとしての一面も聞いてみた。
「エスポワールではシカ以外にも、イノシシ、クマ、カモ、アナグマやハクビシンなども扱っています。特に米やもみ殻を食べたカモは脂が白くてとてもおいしいんですよ。昆虫や雑草を食べているカモの脂は黄色っぽくなるんですが、米を食べて太ったカモは脂の色が真っ白なんです」
山の恵みを巧みに生かし、料理人の技と感性で記憶に残る一皿に仕立てる――それがエスポワールのフランス料理。
この日、藤木シェフが用意してくれたのは「鹿肉のポワレ」。香ばしく焼き上げた鹿肉にソースと季節の野菜を添えた、滋味豊かな一皿だ。

フライパンにバターを入れ、肉を入れてから火をつける。熱したフライパンに肉を入れると表面が硬くなってしまうので、冷たい状態から徐々に火を入れていく

フランス料理でいう「アロゼ」という技法で、ゆっくりじっくりバターを回しかけていく
鹿肉はストレスがかかるとおいしくない。だから罠にかかったらすぐ仕留めてあげるのが適切なのだという。
「ストレスがかかると体温が上がるんです。鹿は通常でも40度以上体温があるんですが50度くらいになってしまうんですよ。そうすると自分の体温で肉が蒸れてしまうんです、低温火傷の状態ですね」
この日は雌鹿のロースを使用。柔らかさで選ぶならやはりロースが適しているという。
「でもね、筋肉をよく使う部位のほうが、実は味があるんですよ。たとえばスネ肉なんかは、しっかりとした旨みがあるんだけど、肉質はどうしても硬くなる。だから調理法との相性が大事なんです」
鹿だけでなく、猪や鳥類などから出る肉以外の部位もすべて廃棄せず、赤ワインと一緒に丸2日間かけて煮込みソースにする。「フォンドジビエっていうんです。骨やスジも捨てちゃいけない、すべてを余すことなく使うことが“命をいただく”ということです」と藤木シェフ。

「来週末、自民党本部でクマ肉をふるまうんですよ。熊の被害がたくさん出ているので駆除は必要ですが、ただ殺すだけだと非難や反発もある。だからこそ、命をきちんと生かしているということを、国民に見せていくべきだと思うんです」
日本ジビエ振興協会の代表理事として、そしてフランス料理のシェフとして、常に命と向き合う料理のあり方を考え続けている藤木シェフ。
山の恵みを余すことなく生かし、ジビエに苦手意識を持つ人々の記憶を上書きする。その一皿には、地域と向き合いながら積み重ねてきた経験と素材への敬意がこめられている。

入口のエントランスに掲げられた鴨の絵画。調度品にもジビエの想いや敬意が宿る

“料理を食べる”ではなく“蓼科を味わう”空間の提供する同店。宿泊も受け入れており、客室は3室そろう
〈オーベルジュ・エスポワール〉
住所:長野県茅野市北山5513-142
電話番号:0266-67-4250
営業時間:ランチ12時~13時30分LO、ディナー17時45分~19時LO
定休日:木曜
HP:https://www.auberge-espoir.com/
Google Map:https://maps.app.goo.gl/LJ2TNh3ddeacgrzx5
撮影:宮崎純一 取材・文:大塚真貴子
閲覧に基づくおすすめ記事