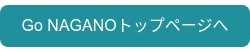野沢温泉村のブナ林と水の物語

訪れたのは、命の煌めきを感じる夏。スキー客でごった返す冬とは打って変わって、落ち着いた風情ある温泉街を歩けば、縦横無尽に張り巡らされた水路を流れる豊富な雪解け水。かすかに硫黄の香りが鼻をかすめ、13の共同浴場や温泉を活用して野菜などを洗ったりする村人の台所や洗濯場などが点在し、豊富な水の恩恵と共に生きる村人の暮らしを垣間見ることができます。
このこんこんと絶え間なく湧き出している水や温泉は、温泉街の背後に聳える毛無山のブナ林がもたらした恵み。豊かな水が育まれる環境やその理由を探るため、水の源流やブナ林を訪ねました。

向かうのは数ある水源のうちの一つ、毛無山の峰続きの山中にある赤滝。
野沢温泉マウンテンリゾート観光局の事務局でガイドも務める河野将城さんの案内のもと、滝から流れ落ちる赤滝川を遡上するように、赤滝登山道を登っていきます。
標高1,650メートルの毛無山に対し、登山道の入り口は標高1,000メートル程度。里に近いほうはブナ林ではなく、木材に使うために戦後植林されたスギなどの針葉樹の林だそう。沢のそばにはミズナラやサワグルミなど、水の近くで育つ木々が自生しています。

透明度の高い水が流れ出し、水音が耳に心地よい

真ん中のあたりによく見るとサンショウウオの姿が
生い茂る草木の緑と、心地よい川のせせらぎ。木漏れ日できらきらと生命力溢れる森の中をひたすら歩き進めます。
「この川にはサンショウウオやイワナがいて、こどもの頃よく探しに来ました」と、河野さん。川の中にある岩の裏をめくると土に潜んでいるそうで、10度以下の冷たい川の流れに癒されながら、その姿を探します。すると、本当にいました!2〜3センチほどの黒いサンショウウオが、素早く川の中を泳いでいきます。サンショウウオがいるということは、豊かな自然環境が保たれ、水がきれいな証拠だそう。

途中、登山道から脇道にそれて水脈の異なる複数の滝を眺めたり、岩場を鎖で登ったり、飛び石で川を渡ったりしながら登ること約1時間。ようやく赤滝へ到着しました。
元は火山だったという毛無山の噴火によって形成された大きな溶岩石の上から水が吹き出し、岩肌を滑り落ちるように落差19メートルほどの滝が緩やかに美しく流れ落ちています。ここから水の旅が始まり、谷間を縫って川となり、農業用水として村の田畑を潤し、やがて千曲川へと合流していくのです。静寂な森に包まれ、光に照らされた滝の姿は神々しく、すべての命の根源を目の当たりにしてありがたい気持ちで満たされました。

上ノ平高原のブナ林

樹齢数百年と思われるブナの木々
今度は野沢温泉村の水が豊かな理由の鍵を握る、毛無山のブナ林へ。
「ブナは保水のために植えられたとかそういうわけではなく、昔から山に自生している天然林です。毛無山の山頂を中心に半径約1キロの円の範囲には、1000年以上前に毛無山が噴火したあとに自然に育ってきた、古代より手付かずのブナの原生林も一部あります」。
そんな貴重なブナの原生林をはじめ、山頂から少し降った標高1,200〜1,300メートルの上ノ平高原には、「湯の峰」と呼ばれるブナの極相林が広がっています。湯の峰の名の通り、このブナ林が温泉のもとになると考えられ、あまり開発しないようにと、野沢温泉の温泉や水利権、山林を管理する「野沢組惣代」によって江戸時代より守られてきました。
一面に広がるブナ林は、土地が平らなので木がまっすぐにのび、雪が積もることから幹の高い位置で枝分かれし、下のほうは雪に洗われて色白できれいな肌の色をしているため、「美人林」とも称されているそう。白っぽくてつるっとした木肌と、すらっと高くのびた幹、空を覆い尽くすように広がる枝葉の緑。美しい風景に心安らぎ、自然と呼吸が深まります。

ブナの葉が積み重なった土はふかふか

ブナの若木。枯れてはまた新しい命が生まれ、果てしないサイクルが繰り返される
ブナの大きな根っこは土に深く広く根を張り、しっかり土をキープして土が流れないようになっており、その上に秋になると葉が落ちて積み重なっていきます。その葉を微生物や昆虫が分解していきますが、ブナの葉は分解されにくく、土になるまでに時間を要するので、何層にも落ち葉の厚い層ができていきます。その層がスポンジのような役割を果たし、雪や雨の水をたくさん蓄えてくれるのだそう。林の中を歩いていると、まるでウッドチップを敷いているかのように地面がふっかふかです。
ここで河野さんから「ブナの葉ってどんな形か分かりますか?」と質問が。答えを考えあぐねていると、「見てください。葉はギザギザの尖ったところから葉脈がのびることが多いのですが、ブナはギザギザの窪みから葉脈があるので、そこが水の通り道になっているのです。雨が降ると、この葉脈を流れ幹を伝って、根元へと水を集め、木の肌には“樹幹流”と言われる水の流れた跡も見られます」とのこと。ブナは水を保水するだけでなく、集めてくることも得意なのです。

「ブナは1本で年間8トンの水を蓄える、森のダムと言われています。ここにある全てのブナが8トンずつ水を蓄えていると思うと、相当な水の量になりますね」と、河野さん。
蓄えられた水は地中へと浸透し、毛細血管のように水脈が張り巡らされ、様々な場所で湧き出しています。先ほど訪れた赤滝もその一つ。さらに深い土の層や小石の層などを通って濾過された地下水脈は、20年ほどで麓の温泉街へ湧水として湧き出し、もっと深い層でマグマの熱に温められ50〜60年かけて湧き出すのが温泉なのです。常に源泉掛け流しの新鮮なお湯で満たされる野沢温泉は、50〜60年前に降り積もった雪や雨なのだと思うと、目に見えない自然の循環と恵みに尊さを感じます。

そんな水の恩恵にあずかってきた野沢温泉の村人たちは、水を保全し持続可能な暮らしを維持するため、植樹活動を行なっています。「ブナの森100年構想」を掲げ、使われていないゲレンデの一部をブナの森に戻そうと、観光局やNPO法人「おせっ会」が中心となって植樹をつづけているほか、地元の小学生や中学生、友好都市の体験学習旅行や一般向けの植樹ツアーでも、ブナ林を見て水の話をしてから植樹に協力してもらっています。
「植えてから立派なブナの木になるまで60〜80年くらいかかると言われています。これで20年目。広さは東京ドームと同じくらいになりました」。山やブナ林の美しい原風景、水がもたらす生活や文化をこの先もずっと残していくため、未来を見据えて行動を続けているのです。
清らかな湧水が醸す、個性溢れる酒を巡る

自然の循環が生み出した、清らかで豊富な冷たい湧水。村人は汲んで畑仕事の合間に飲んだり、お茶を淹れたりなど、飲料水として日常的に使用しています。
おいしい水があるということは、必然的においしい酒も生まれるというもの。この地域の湧水を生かして育まれた、3つの個性豊かな酒を巡ります。
「田中屋酒造店」の日本酒、「水尾」

野沢温泉村の隣、飯山市にて明治6年(1873)に創業した「田中屋酒造店」。仕込み水に野沢温泉村の毛無山のほど近く、水尾山の湧水を使用していることから、「水尾」という名の酒を醸しています。
スタッフの佐伯幸子さんの案内のもと、蔵の中を見学。日本酒ができるまでの工程ごとに部屋を移動しながら説明を受けます。まずは原材料のお米を洗って浸漬し、蒸しあげる場所、その蒸したお米で米麹をつくる麹室、お酒を仕込むタンクが並ぶ仕込み蔵、製品化に向けて洗瓶や充填、ラベル貼りなどの作業が行われる蔵、冷蔵の保管庫と、ひととおりを見ることができます。
日本酒の種類、原材料やその役割、それぞれの工程でどのような作業が行われるか、蔵人の技術や努力など、奥深い日本酒の世界を堪能しながら、日本酒の醸造について目と耳で学ぶことができる貴重な体験です。

案内をしてくれた佐伯さん。丁寧に分かりやすく日本酒の製造工程を教えてくれます

精米歩合の違いを実際の米で比較

酒を仕込むタンクがずらり

地酒「水尾」を仕込むため、水尾山から汲んできた水が入ったタンク
この蔵の酒の何よりの特徴は、その原材料。
「水尾の酒に使われる米は、ひとごこちと金紋錦。長野県の気候や環境で育ちやすいよう、長野県で開発された酒米で、蔵の5キロ圏内で育てられています。また仕込み水は水尾山の湧水を使っていますが、この水は世界的に見ても超軟水で、甘さのある名水なのです。
以前は蔵の地下水を使用していましたが、水質が低下したこともあり、お酒に適した水を探しまわっていろいろと試した結果、水尾山の水のおいしさに社長が惚れ込み、地元の協力を得て使わせてもらうようになりました。仕込みの時期には2日にいっぺんほど、2トントラックで汲みに行きます。この水のおかげで、おいしいお酒ができているのです」。

水尾のおいしい酒を試飲

「令和6酒造年度 全国新酒鑑評会」で金賞を受賞した大吟醸など

チェイサーに仕込み水
直売所にある試飲スペースへ移動し、その仕込み水を試飲させてもらいました。やわらかさと甘みを感じるとてもおいしい水で、すーっと体に染み渡ります。つづけて水尾の酒も。米の種類や精米歩合、酵母の種類、発酵のさせ方などで、普通酒から大吟醸までお酒のラインナップも豊富。キリッと辛口だったり、飲みやすかったり、甘口で香りが高かったりと、それぞれに味わいが異なるので、飲み比べて自分好みのものを見つけます。
「良い素材を全国から取り寄せることもできますが、私たちはこの土地でとれたものを、この土地で醸す、そんな“ここでなければ造れないものを造る”ことを大事にしています。その土地の気候で育った野菜や米を使った料理には、やはりその土地で造られた酒が合う。そんなテロワールを感じに、ぜひ足を運んで味わってもらいたいです」。水尾の酒造りの背景や想いに触れて飲む酒は、より一層格別でした。
「野沢温泉蒸留所」のジン

野沢温泉のメインストリート、大湯から歩いて3分ほどの場所にあり、2022年にオープンした「野沢温泉蒸留所」。
ウイスキーとジンを造っている蒸留所で、野沢温泉の湧水「六軒清水」や、地元の山々で採れた草木などのボタニカルを使用して蒸留を行なっています。
元缶詰工場をリノベーションしたというスタイリッシュな外観が目を引く蒸留所に入ると、手前の棚には樽詰めしたウイスキーがずらりと並び、奥にはドイツから輸入したという大きな蒸留器のほか、缶詰工場時代の機械を再利用したバーカウンターと、おしゃれな空間が広がります。

ガラス越しに見られるかっこいい蒸留器

熟成中のウイスキー樽が並ぶ

缶詰工場時代の機械でつくったバーカウンター
代表のオーストラリア人、フィリップ・リチャーズさんは、長野オリンピック後に野沢温泉を訪れた時、ほかのスキーリゾートとは異なり、温泉や祭りなどの文化や歴史が息づき、歩いて巡れる範囲にすべてがあるこの土地に惚れ込んで、その後移住。もともとお酒好きで、おいしい水と豊かな自然があるこの土地なら絶対においしいお酒が造れると、仲間たちと一緒にこの蒸留所を立ち上げました。野沢温泉をもっと知ってもらい、冬だけでなくグリーンシーズンにも訪れてもらう目的地の一つになればという想いもあり、野沢温泉への深い愛を感じます。

ジャパニーズウイスキーは3年間熟成させるという決まりがあるため、まだ販売には至っておらず、現在は定番商品で4種類のジンを扱っています。
「それぞれにコンセプトがあり、森をイメージした『NOZAWA GIN』、スキーの後の夜の街をイメージした『CLASSIC DRY GIN』、長い冬が明けて芽吹きが始まり、農作物の収穫への祝福をイメージした『IWAI GIN』、加水に地元の紫蘇ジュースを加えて春の味わいをイメージした『SHISO GIN』があります。ラベルのマークは水や季節の循環を表していて、ボタニカルには地元のクロモジやスギ、山椒など、野沢のものも多く使われています」と、広報担当の市川三和さん。

さっそく4種類をテイスティング。まずはロックで香りや味を楽しみつつ、チェイサー用の六軒清水の水、氷と炭酸水もあるので割って飲みます。ソーダ割りにすると炭酸と一緒に香りが弾け、さわやかな森の香りを感じたり、清涼感を感じたり、華やかさを感じたり。
「ジンは使用するボタニカルによって地域を表現できるお酒なのです。それに加え、まろやかな超軟水の湧水が、より一層植物の味を引き立たせています」という市川さんの言葉どおり、このジンを飲むと、ふしぎと先ほど訪ねたブナ林の景色が蘇りました。
まるで野沢温泉の風土をそのまま閉じ込めたかのようなお酒。世界へ発信するため、輸出も見越していますが、「地元でできたジンは、やはりこの土地でとれた山菜など、地元食材を使った料理と合わせて味わうのが一番。ほかではできない贅沢な体験だと思います。お酒を楽しみに、ぜひグリーンシーズンに来てほしいですね」と、やさしく話してくださいました。
「山ぼうし」のどぶろく「嘉太郎(かたろう)」

野沢温泉蒸留所から歩くこと5分。温もりある木製看板の「山ぼうし」が目印の民宿に、宿主の小嶋淳さんが造る名物のどぶろくがあると聞いてやってきました。
秋田県出身のご主人は、スキーが好きで野沢温泉を訪れ、この村の温泉や祭りなどの文化、人の温かさ、水のおいしさなどが気に入って住むようになり、今から25年前に民宿を開業。「野菜など自分が作ったもので喜んでもらいたい」という想いや、その優しく親しみやすい人柄で多くのスキー客を出迎えてきました。

もともと日本酒やどぶろくといったお酒が好きだったこともあり、村に構造改革特区制度を活用する話が持ち上がった際に、どぶろくを提案。紆余曲折を経て、20年前の平成17年に村が「湯の郷どぶろく特区」に認定されたことで、どぶろくを造り始めました。
どぶろくの原材料であるコシヒカリの米は無農薬で作っており、田んぼ2枚分をどぶろく用にして、田植えや稲刈りをイベント化してみんなで育てているそう。水は近所の「六軒清水」。「ほかの湧水でも試したけど、六軒清水が一番しっくりきた」と話します。そこに米麹と酵母を加えて発酵させ、2ヶ月ほどで完成。宿泊客に提供するほか、村内の酒屋2軒でも四合瓶で販売されています。
上質な水と米で仕込まれるどぶろくは、言うまでもなくおいしいはず。それを裏付けるように、どぶろくの全国コンテストでも何度も入賞していると言います。
地元民宿で滋養に満ちた料理と酒を味わう

今夜は宿に泊まって、おいしいどぶろくとご飯をいただきます。この日は信州みゆきポークの冷しゃぶ、野沢温泉の清流で育ったイワナの刺身、郷土料理の塩煮イモ、ナスやトマト、ゴーヤなどの夏野菜を使ったサラダや寄せもの、揚げ浸しなど、全部で10品ほど。
ほとんど自分たちで育てているという旬の野菜を使って、小嶋さんの奥様が作られる料理はどれも丁寧で美しく、瑞々しい野菜のパワーを感じます。また自家製米は7分づきにしており、「玄米ほど食べづらくなく、栄養分を残した形で、お客様の健康を考えた」とのこと。一つひとつに愛情がこもっています。

そして料理に合わせるどぶろく。この日は製造して2ヶ月ほどの若いもの、六軒清水を炭酸にして仕込んだ「どぶぺり」、3ヶ月熟成させたものの3種類。それぞれ飲み比べると、若いものやどぶぺりはピリッとしたりシュワっと感があって飲みやすく、熟成のものはどっしり飲み応えがあり、どれも濃厚で芳醇な米の旨みと香り、まろやかさを感じておいしいです。
春は山菜。夏は野菜。秋はきのこ。冬は野沢菜などの保存食。すべてが毛無山と水がもたらした恵み。「この自然が村の宝ですね。季節のものを食べて、どぶろくがあれば、もう最高」と、気さくで温かい宿のご夫婦と語らいながら、おいしいごはんとお酒に心と体が喜んでいました。
森と水の恵みに生かされていることを実感する、野沢温泉村

野沢温泉の山と雪、そこから生まれる水の物語と、人々の営み。すべてが繋がって循環していること、それをこの村の人たちは理解して大切に守り、その恩恵を享受していました。
水が生まれるブナ林を見て、その水から醸される酒を味わい、村人と語らい、温泉に入って。コンパクトな村だからこそ、自然と暮らしと観光がひと続きになっており、その中に身を置くことで、私たちは自然に生かされ、自然の一部であるのだということをはっきりと思い出させてくれました。
五感が研ぎ澄まされ、ここで過ごした空気も会話も味わいも丸ごと、あの澄んだ水のように私の体に染み込んでいく。それはきっと私の心を豊かにし、生きる力を与えてくれる。六軒清水で淹れたコーヒーを飲みながら、そんなことを考えていました。
野沢温泉の水が結ぶ酒旅 ~日本酒・GIN・どぶろく~
記事で紹介した3つの酒文化を巡る1泊2日のツアーを開催しています。オプションでブナ林を散策するトレッキングも実施。詳細は野沢温泉マウンテンリゾート観光局のホームページをご覧ください。
https://nozawakanko.jp/spot/spot-10292/
開催日/2025年9〜11月の水曜(2026年度も開催予定)
予約/7日前の17時まで
料金/大人1名35,000円 ※最少催行人員は2名様(2名様1室のご利用)
問い合わせ/野沢温泉マウンテンリゾート観光局
https://nozawakanko.jp/
travel@nozawakanko.jp
取材・文:佐藤 妃七子 撮影:花岡 凌
閲覧に基づくおすすめ記事