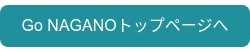TOP PHOTO:キラキラと輝くススキ原や紅葉は、秋山ならではの美しさ
秋山には、夏とは異なる魅力とリスクがある

澄んだ青空、涼しい風、燃えるような紅葉……。山が好きな方は、秋の美しい信州の山々にも、ぜひ足を運びたいと思っていらっしゃることでしょう。
秋とひとくちに言っても、初秋・中秋・晩秋で山の状況は大きく変化します。さらに信州は南北に長く、里山から3000m級のアルプスまでさまざまな山を抱えているため、山の位置や標高によっても状況がかなり違います。
標高によっては初冬並みの寒さになることもありますし、日本海側の山では他の山よりも一足早く降雪に見舞われたりもします。リスクも内包する秋の山ですが、どのようなリスクがあるかを把握し、対策を十分に行えば、夏とは違う魅力をたっぷり味わうことができます。
秋の天気の特徴①台風と秋雨前線
まずは秋の天気の特徴を知り、注意すべきポイントを押さえましょう。
秋の悪天候の代表といえば台風です。日本における台風の発生・接近・上陸数は7月~10月にかけて最も多くなっています。近年は温暖化の影響で秋も海水温の高い状態が続き、10月に日本列島近くを通る台風が増えている傾向があるとも言われています。
【図1】は、長野県に台風被害をもたらす傾向のある台風のコースです。
最悪なのが、県内を通過する①のルート。全県的に大雨と強風の被害が発生し、千曲川水系では厳重な警戒が必要となります。また、長野県に接近して西側を北上する②のコースも、県全域に暴風・大雨をもたらします。特に木曽川、天竜川水系では厳重な警戒が必要です。
県の東側を北上する③のコースは、県東部や北部で大雨や強風に対する厳重な警戒が必要となります。④は太平洋側を東に進むコースで、伊那谷や木曽谷、佐久地方などを中心に大雨となります。⑤は北部の山沿いで強風となり、特に北アルプス一帯では強い風、雨となるので注意が必要です。
季節の変わり目である秋には「秋雨前線」が発生し長雨になることもあります。秋雨前線が停滞しているときに台風が接近すると、前線の活動が活発になり、災害級の大雨がもたらされることもあります。2019年10月12日~13日に、千曲川が氾濫して北陸新幹線の基地が水没する大雨災害をもたらした台風19号は、このパターンです(【図2】)。
秋の天気の特徴②秋晴れと冷え込み

台風や秋雨前線の季節が終わり、日本付近が大陸の高気圧に覆われると、ようやく登山者にうれしい「秋晴れ」の季節が訪れます。この時期になると、山にもスッキリとした青空が広がるようになります。これは、大陸生まれの移動性高気圧が、比較的寒冷で乾燥しているからです。
加えて山では気温がぐっと下がり、標高の高いところから紅葉が見頃になるところも多くなってきます。紅葉前線は山頂付近からはじまり次第に山麓へと広がっていきます。

信州では秋の冷え込んだ朝に「霧」が発生することが多くなります。【図3】を見ると、気象台や観測所の平年の月別霧日数は、諏訪と軽井沢を除いて秋に多くなっています。
盆地や平地に広がった霧を山の上から眺めると、足元に一面雲が広がった「雲海」として景色を楽しむことができます。これぞ山岳県・信州の秋の風物詩と言えるでしょう。

なお、標高の高い山では季節が一足早く進みます。白馬の栂池自然園の紅葉の見頃は9月下旬~10月上旬。10月に入れば降雪の可能性もあります。秋が深まるにつれ、寒気が流入しやすくなり、高い山々は雪を冠する頻度が高くなります。
この時期、アルプスなど標高の高い山では「三段紅葉」という特別な景色が見られることがあります。山麓の針葉樹の緑色、山腹の紅葉の赤色、山頂付近の雪の白色が同時に見られる光景のことです。
【図3】の注
※1:月別霧日数の平年値統計期間は観測所ごとに異なります。
長野1991~2019年/松本2007~2020年/諏訪1997~2020年/軽井沢2009~2020年/飯田2006~2020年
※2:松本の2~5月の月別霧日数平年値は、欠測などの理由により平年値の統計年数が不足しているため、空白としています。
※3:長野の月別霧日数の平年値は、平成31年の目視観測の終了により統計を切断したため、切断前までの期間の値で求めた平年値(参考値)です。
秋山登山のリスク①日没時間の早さ

秋山登山の注意点として、まず挙げられるのは「日没時間の早さ」です。
長野の日の出・日の入り時刻を調べると、お盆の8月15日は5:04日の出、18:39日の入となっています。それが10月10日には5:50日の出、17:18日の入りになります。日の出は約45分遅く、日の入りは約1時間20分早まります。
山では木々や山の影で、日没時間よりも早く暗くなることもあります。また、夕方は野生動物の活動が活発になります。
日没が近づくと焦りが生じ、道迷いや転滑落などの遭難につながりやすくなります。仮に遭難した場合、日没以降は救助活動が難航してしまいます。
不測の事態も考慮すると、日没の2時間前には下山できるように計画したいものです。15時~15時半には行動を終えられるように、余裕をもった計画を立てましょう。そして、日帰りでも必ずヘッドランプは持つようにしてください。
秋山登山のリスク②寒さ

標高が100m上がると気温は約0.6度下がります。つまり、標高1000mの山と3000mの山では気温が10度以上違う計算になります。
アルプスなどの高山では、登山口は1000m程度で山頂付近が3000m前後という山もあります。山麓で雨に降られたあと、山頂で雪になるのは最悪のパターンで、濡れたウェアが凍って体が一気に冷えてしまい、低体温症になる恐れもあります。ロープウェイなどで一気に標高を上げる場合も、上部の天気に気を付けましょう。
秋山登山に、レインウェアなど防水・防風性能のあるアウターは必須です。また、フリースやダウンジャケットなどの防寒着も用意しましょう。手袋やニット帽、ネックウォーマーなどの防寒小物もあると便利です。
秋山登山のリスク③天候による状況変化

台風の大雨で登山道が崩壊したり、沢が増水したりすることがあります。台風の時に登山をする方はあまりいないと思いますが、台風直後に登山を予定している方は、通行止めになっている登山道がないかなど、最新の情報に気を付けてください。
中秋~晩秋にかけては、登山道の凍結や霜、積雪に注意が必要です。木道などは霜や凍結で非常に滑りやすくなります。岩場の下りなどは滑って転滑落につながる恐れもありますので、状況によっては無理をせずにプランを変更することも考えましょう。
秋山登山のリスク④交通機関や山小屋

ここまで気象的な点を中心に注意点を紹介しましたが、このほかにも秋山ならではの“落とし穴”がいくつかあります。
山小屋は通年営業の小屋を除き、多くは9月末~10月半ばごろに営業を終了します。また、ロープウェイやバスの運行が夏シーズンから変更になることも多く、朝いちばんの便が遅くなるケースでは登山開始時刻も遅くなってしまいます。
また、紅葉シーズンの週末などは大変な混雑になることもあります。私も過去にいくつか体験がありますが、高速道路が大渋滞して登山口に到着できたのが夕方になってしまったということがありました。また、ロープウェイ乗車が3時間待ちだったこともありました。
思いがけない状況になったときは、無理せず柔軟に計画変更を。サブプランを用意しておき、短い行程のハイキングや、山麓の観光に切り替えるのもおすすめです。
日ごろからトレーニングを!

トラブルを避けるため、またはトラブルに遭ったときに適切な対応を可能にするために、最も大切なことは、やはり「体力をつけておくこと」だと思います。装備や計画にも増して、体力は登山における重要な要素。ある程度休まずに歩き続けられる持久力があれば、寒さで体が冷えることも避けられますし、十分な筋力があれば歩きづらい路面にも対応できます。
体力に余裕があるだけで、安全性がぐっと増すのが「登山」です。日ごろからトレーニングに励み、余裕をもって秋山を楽しんでください。
撮影・文:横尾絢子
<著者プロフィール>
横尾 絢子(Ayako Yokoo)
編集者・ライター。気象予報士。高校時代より登山に親しむ。気象会社、新聞社の子会社を経て、出版社の山と溪谷社で月刊誌『山と溪谷』の編集に携わる。2020年、東京都から長野県佐久市に移住したのを機に独立。六花編集室代表。現在はフリーランスとして、主にアウトドア系の雑誌や書籍の編集・執筆活動を行なう。プライベートではテレマークスキーやSKIMO(山岳スキー競技)を中心に、季節を問わず山を楽しんでいる。日本山岳・スポーツクライミング協会SKIMO委員。
閲覧に基づくおすすめ記事